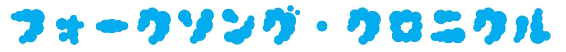いつ頃から、歌はあったのだろう。
人類が誕生して、どれくらい経ってから?
想像してみよう。
「はじめ人間ギャートルズ」みたいな地平線の続く大地。
あっちのほうから、太鼓か何かの音が聴こえる。
骨でつくったような楽器の音もする。
「マンモスが~とれた~よ~」
すると、また別のほうから、太鼓と骨と、人の声。
「こっちもさかな~やけた~よ~」
それはまだ、言語が生まれる前の話。
原理原則がなく、統一されていない、言葉のご先祖様。
つまり、それは歌だったろう。
感情や状況を伝達するための、原始の言葉、「歌」。
おそらく、人は言葉をつくる前、歌でコミュニケーションをしていた。
やがて文明の中で、言語が発明されると、人は言語で歌を歌い始める。
「詩」の誕生だ。
喋り言葉、書き言葉、そして歌の詩・・・同じコトバでも、何故だか少しずつ違う不思議。
世界には無数の言葉が存在する。
そして日本という国の文化は、島国ゆえに、様々な外の文化を吸収しブレンドする。
もちろん、言葉もそのひとつ、歌だってそう。
1960年代後半、海の向こうのアメリカから聴こえてきた音楽があった。
それらは、フォークソング、ロックンロール、ブルース、カントリーなどと呼ばれていた。
そしてそこには、ギターという楽器がつきものだった。
その頃から活躍し、現在の日本のロックやポップスの源流の確かなひとつであるフォークシンガーの大先輩たち。
ちょっと、その人たちの話をしてみたい。
フォークの定義なんか、どうでもいい。
メジャーなフォークとマイナーなフォークとか、日本語ロックと英語のロックとか、政治的なものとそうでないものとか、そういう話をしたいんじゃない。
私はいま、「歌」を歌いたいだけだ。
歌について、歌をつくってきた人たちについて語るのもまた、歌だろう。
過去を振り返り、懐かしんだりするわけじゃないから、安心してほしい。
だいいち、1980年代生まれの私にとって、フォークもロックも何もかも、「いま」でしかない。
1968年を想像するのも、原始時代を想像するのも、同じことだ。
ああ、想像するということも、歌かもしれない。
カラオケじゃないのだ。
著作権を持つ正確な歌詞を決められたメロディーにのせて歌うことが、「歌がうまい」ということだなんて、あんまり貧しい。
と、こうして毒を吐いてみせるのも、また歌である。
もちろん、言葉や声でなくても、歌かもしれない。
世界がどんなに変わっても、あっちもこっちも「いま」だらけであり、それもこれも「歌」なんだ。
やりきれないこともある。
わかりあえないこともある。
歌は、すべての絶望と希望をすくう。
言葉とアコースティック・サウンドが主なフォークソングなら、なおさら。
だから、ちょっと話してみたい。
昔のことは、生まれてないから想像してみたい。
なぎら健壱さんや坂崎幸之助さん、中村よおさん、中川五郎さん、岩田由記夫さんといった方たちのお書きになるフォーク史、音楽史のようには書けないけれど、私なりの新しく面白いものを書いていこうと思います。
なお、タイトルが「フォークソング・クロニクル」とありますが、この連載で取り上げさせていただくミュージシャンは、いわゆるフォークシンガーとは限りません。
内田裕也さんやサザンオールスターズだって書くかもしれません。
私は、この連載で、「フォークソング=民謡=みんなのうた」という考えを示したいのです。
(そしてまた、「みんなの歌」は「私の歌」)
すべての歌はフォークソングである。
そもそも、フォークもロックもブルースも、ひとつの音楽。
それらアメリカ音楽の起源を遡れば、わかります。
ロックという言葉が、音楽様式よりも生き方の精神としての意味で使われているように、フォークという言葉も、生ギターで弾き語ることではなく、ひとつの生き方なのだ。
生きていこう。
そして歌おう。
|
次の記事