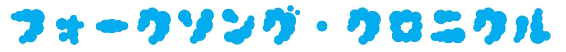皇居の一般参賀で、奥崎謙三が昭和天皇にパチンコ玉を発射したその翌日。
1月3日、新宿西口公園もまた、騒乱の最中だった。
唐十郎率いる状況劇場が、東京都の中止命令を無視し、西口公園に紅テントを建て、芝居をやってのけたのだった。
200名ほどの機動隊にテントが囲まれる中、上演される「腰巻きお仙」。
それはまさに、人間界の常識を知らぬまま、都市に忽然と燃え上がるひとつの大きな炎だった。
芝居が終わり、唐十郎、李麗仙ほか、都市公園法違反で逮捕。
1969年、東京は、あちこちが燃えていた。
いや、日本中、世界中が燃えていた。
ジャズ喫茶などでのライブ活動を続けていた、内田裕也プロデュースによるバンド、フラワーズは、1月にリリースしたシングルに続き、アルバム「チャレンジ」をリリース。
メンバーの内田裕也、麻生レミらがヌードになったジャケットは、印象的である。
フォークが隆盛をほこった時代、ロックンローラー内田裕也の戦いは続く。
軽快なドラム音の中を失踪するように歌うボーカルが、かっこいい。
寺山修司の劇団天井桟敷の団員だったカルメン・マキは、「時には母のない子のように」でデビュー。
当時17歳。
この歌は世間の批判もあったが大ヒットし、紅白歌合戦にも出場する。
そして、アルバム「真夜中詩集〜ろうそくの消えるまで〜」をリリース。
「時には母のない子のように」の大ヒットで、CBSソニーの社長からプレゼントされたレコードの中に、ジャニス・ジョプリンのものがあった。
そこから、カルメン・マキはロックへ転向していく。
夏。8月9日から10日。
2日間にかけて開かれたのは、「全日本フォークジャンボリー」。
いわゆる、第1回中津川フォークジャンボリーである。
参加者2000人から3000人。入場料800円。
夜6時から翌朝9時半までの祭り。
出演は、高石友也、岡林信康、中川五郎、高田渡、遠藤賢司、五つの赤い風船、岩井宏、ジャックス、上条恒彦、田楽座。
黎明期のフォーク&ロックの革命児が集まった。
運営は、中津川労音事務局から生まれたフォークジャンボリー実行委員会。
局長の笠木透もまたフォークシンガーである。
商業的な側面は一切なし。言葉と歌の職人たちによる、手作りのフェスティバル。
ウッドストック・フェスティバルが、同年の8月15日から17日の開催なので、このような大規模な野外コンサートとしては世界初とも言える。
そして、この第1回全日本フォークジャンボリーにて、ジャックスは解散した。
彼らは、7月の「第5回ジャックス・ショウ」にて解散を宣言していた。
ジャンボリーから2ヶ月後の10月、セカンドアルバム「ジャックスの奇蹟」ならびにシングル「ジョーのロック」をリリースし、奇妙で尖ったプログレッシブ・ロックの幕は、静かに、しかし色濃い影を残しつつ、閉じられた。
暗くて、暗くて、かっこいい。
で、ウッドストック・フェスティバルと同じ日程で行われたのが、「第4回フォークキャンプ」。
場所は、びわ湖サンケイバレー。そして打ち上げコンサートなるものが京都円山野外音楽堂で開かれた。
出演者は、岡林信康、中川五郎、遠藤賢司、五つの赤い風船、高田渡、若林純夫、ザ・ディラン、友部正人、西岡恭蔵、中山ラビ、フォークキャンパーズ、なれあいシンガーズ、豊田勇造、藤村直樹、勝木徹芳、やまたのおろち、アップルパミス、マヨネーズ、阪大ニグロ、三つの赤いシャックスとえんどう豆の木。
「アンドレ・カンドレ」
9月、東京のCBSソニーに、奇妙な名前の青年が立っていた。
彼の本名は、井上陽水。陽水と書いて「あきみ」と読む。そう、のちの井上陽水(ようすい)だ。
ビートルズに憧れ、そしてフォークルの「帰って来たヨッパライ」を深夜放送で聴き触発され、歌い始めた。
春頃に福岡に住んでいたとき、RKB毎日放送の「スマッシュ!!11」という番組の視聴者参加コーナーに、自作の曲をテープに吹き込んで持ち込んだのが、注目された。
その曲名は・・・。
「カンドレ・マンドレ」
ああ、最初から、井上陽水は生きることの簡単さを教えてくれている!
さらに、「カンドレ・マンドレ」へのリクエストの葉書は、彼が友人知人に頼んで送らせたものがほとんどだという・・・。
スバラシイ!
そして9月1日、デビューシングル「カンドレ・マンドレ」はリリースされた。演奏は六文銭、編曲は小室等。
続くセカンドシングル「ビューティフル・ワンダフル・バーズ」は、松山猛との作詞、加藤和彦の作曲。
こうしてフォークの先達たちのサポートを受けてのデビューだったが、いずれもヒットはしなかった。
アンドレ・カンドレの芸名も、3枚目のシングルを最後に使わなくなった。
井上陽水として生まれ変わるまで、時間が必要だった。
名前をなくした若き天才は、いったん闇へ潜る。
「下痢を治しに行ってきます」
この書き置きは何だ。
岡林信康の筆跡だ。
第1回全日本フォークジャンボリーおよび第4回フォークキャンプを終えた岡林は、疲弊していた。
アンドレ・カンドレがデビューした9月、岡林は3ヶ月ほどの仕事のスケジュールを残したまま、ひとりどこかへ失踪した。
URCは、第5回配付の「第4回フォークキャンプコンサート」、秘密結社○○団「あくまのお話し」を最後に、会員制組織を廃止。
秘密結社○○団は、金延幸子、中川イサト、村上 律、瀬尾一三、松田幸一によるアシッド・フォーク・グループ。
高田渡のURCの2枚目のアルバム、「汽車が田舎を通るそのとき」。
進行役のような女の人と喋りながら、歌を吹き込んでいるスタイルなのだが、見事に話が噛み合っていない・・・。
ちょっとイライラしている高田渡と、どうしていいのかわからない女の人と、なんだか聴いていて落ち着かなくなってしまう。
それはそれとして、この歌たちを歌っているのがほんとうの二十歳そこらの少年だろうか。
もはや、すでにたくさんの旅をしてきた熟練の詩人。
それはそうだ、彼は生まれたときから旅をしていた。
静けさと深みのある空間に、若き高田渡がいる。
ぼそぼそとつぶやくように歌うその声と、選び抜かれ磨き抜かれた言葉、そして優しくも鋭いギターのピッキング。
ジャケットのイラストを書いているのは、実のお兄さん。
エイプリル・フールが結成されたのは、ずばり4月1日。
「フローラル」というバンドの小坂忠、柳田博義(のちの柳田ヒロ)、菊池英二。柳田の兄のバンド「ドクターズ」の細野晴臣。細野がやっていたもうひとつのバンド「バーンズ」の松本零(のちの松本隆)。
この5人によって組まれたエイプリル・フールは、レコーディングやライブ、映画のサウンドトラック、また東京キッドブラザーズの劇中音楽と、活動を繰り広げる。
しかし、6月にメンバー間の亀裂が決定的になる。
細野、松本、小坂は、日本語によるフォーク・ロックやアメリカン・ロックを指向していたが、柳田、菊池はプログレッシブ寄りで、解散が決定する。
そして、アンドレ・カンドレがデビューし、岡林信康が失踪した9月、エイプリル・フールは1枚のアルバムをリリースし、姿を消す。
ジャケット写真の撮影は、荒木経惟。
小坂忠は東京キッドブラザーズの「ヘアー」の出演が決まり、バンド活動から退く。
細野と松本は、新たなバンド構想に、大瀧詠一を誘う。
大滝は、船橋の製鉄会社を退社したのち早稲田大学に入学し、布谷文夫や竹田和夫と友人になり、ライブに飛び入り参加したりしていた変わり者。
細野ともこの頃に知り合い、「ランプ・ポスト」という音楽研究会を開いていた。
そしてギタリストには、林立夫、小原礼と「スカイ」というバンドを組んでいた鈴木茂が選ばれた。
こうして、大瀧詠一、鈴木茂、細野晴臣、松本隆の4人よって、「ヴァレンタイン・ブルー」が結成された。
当時、日本でバッファロー・スプリングフィールドといったアメリカン・ロックは人気ではなく、もっぱらブリティッシュ・ロック花盛りだった。
「イギリスのロックはアメリカのロックの模倣なのだから、日本でロックをやるならアメリカのロックをやらなければいけない」
日本語の歌詞に関しては、メンバー間でも意見が分かれ、細野も大瀧も反対だったが、結局はドラマーでもある松本隆による詩世界が、見事に新しい時代を彩っている。
彼らに共通する、芸能や芸術への憧れや畏敬の念、ユーモア。
そして重く、ときに軽く、激しく優しいリズムと音。
まるで、宮澤賢治がアメリカ西海岸に立っているような・・・。
そんな音楽は、それまでになかった。
「はっぴいえんど」と名を変えるのは、翌年のこと。
ブルースクリエイション、ファーストアルバム「ブルースクリエイション」をリリース。
日本橋生まれの竹田和夫は13歳でギターに触れ、16歳でプロデビューした快児。
初期は、シカゴ・ブルースを志向していた。バターフィールド、マディ・ウォーターズ、ライトニン・ホプキンス、ジュニア・ウェルズなどのナンバーが主に演奏していた。
翌年の1970年までは布谷文夫がボーカルだが、彼が抜けてからは、竹田和夫がボーカルも担当、いまもなお続くバンドである。
南正人は、東京外語大学を休学し太平洋を船で渡って、2年間、地球を旅して日本に帰ってきた不思議な男である。少年時代からの夢だったらしい。
その後、歌をつくって歌い出し、高田渡や遠藤賢司、真崎義博らとともに、フォーク集団「アゴラ」に所属、フォークキャンプやフォークジャンボリーに出るようになる。
彼が青山のクラブで弾き語りのアルバイトしていると、浅川マキのプロデューサーにスカウトされ、できたのがデビューシングル「ジャン」。
URCから、中川五郎のセカンドアルバム「終り、はじまる」。
ベトナム戦争終わらぬ状況下、プロテストソングに疲れ失踪した岡林信康とは真逆に、中川五郎は反戦歌を歌い続ける。
しかし、同時にエリック・アンダーソンの「Come To My Beside」のカバー、「おいでよぼくのベッドに」を歌ったりするのが中川五郎イズムなのである。
そうした反戦とセックスに共通する、つまり愛なるものに対して、彼は実直で、その震えるような声はまるで暗い世界(部屋)を照らすロウソクの灯のようだ。
フォークル解散後。
北山修は、若者のスターだった。ある意味で時代の象徴だった。
彼の芸能活動は、すべてがパロディ、セルフパロディのようだ。
まず彼は、本来が、医者・北山修なのだから、歌ったり喋ったりしていること自体が北山修のパロディともいえる。
自らが自らを演じ、その演じ方も次から次へと変えていく。
1969年の秋、彼はキタヤマ・オ・サムという名だった。
その名を分解し、リリースしたアルバムは『ピエロのサム』。
早川義夫は、ジャックス解散後、早くもソロアルバムをリリースする。もちろんURCからだ。
「かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう」。
有名な「サルビアの花」や「NHKに捧げる歌」も入っている。
思えば、「かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう」とか、「ほんとうにそれは正しいのか」とか、「もっと裏側に意味があるんじゃないか」とか、そんなふうに価値観や考え方を見つめ直すことを、URC系のミュージシャンたちは教えてくれたんだと思う。
先日(2011年11月)、早川義夫さんがtwitterで、「いまは、かっこいいことはかっこいい、かっこ悪いことはかっこ悪いと思ってます」とつぶやいていた。
なんだか、気持ちがホッコリした。
北山修が道化を演じることで北山修として存在する実験を繰り返しているとき、加藤和彦はソロミュージシャンとして出発していた。どちらも違うカタチでのポップ・スターなのだ。
ファーストアルバム「ぼくのそばへおいでよ」。
1曲目は、中川五郎もカバーしているエリック・アンダーソンの「Come To My Bedside」のカバー。
偶然、加藤和彦と中川五郎は、その声色と震えるような囁くような歌い方が似ている。
詩も曲も、音楽という面白さの集約。
ザ・フォーク・クルセダーズという船を降りた加藤和彦の、新たな一人旅が始まった。
12月5日、状況劇場のテント公演の初日に、天井桟敷が葬儀用の花輪を送った。
天井桟敷旗揚げ公演のときに、状況劇場が中古の花輪を送ってきたことへの意趣返しだった。
12月12日深夜、唐十郎たちが天井桟敷館に殴り込みをかけ、大乱闘に。
寺山、唐を含む9人が現行犯逮捕。
「ユーモアのつもりだったが分かってもらえなかった」
「ユーモアのつもりなら自分で持って来い、そもそも話を聞こうと思って行っただけ。これは殴り込みではない」
東京は・・・燃えていた。
いや、いまも変わらない。特に新宿辺りは・・・。
高石友也、大阪フェスティバルホールでの「サヨナラコンサート」を最後に、渡米。
日本でフォークソング・スピリッツの種を蒔いた男は、ひとり海を越え、アメリカへと姿を消した。
1969年が、暮れていった。