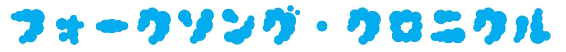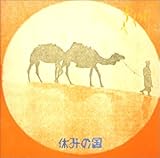メキシコシティ、中心部。
あるホテルのロビーに、その絵はあった。
縦5メートル以上、横30メートルほどの大きな壁画。
中央には骸骨のようなヒトが全身を広げ、まるで爆発の瞬間のようだ。
周りを稲妻のような光がほとばしり、また顔のついた炎のようなものも燃えさかる。
巨大なファスナー、赤いクジラのような怪物、極彩色のイメージ。
隅のほうには、子供のような黒い雲が浮かんでいる。
これは何を描いているのだろうか。
メキシコのホテルのロビーに飾られたこの巨大壁画には、「HIROSHIMA NAGASAKI」とタイトルがつけられていた。
描いたのは、岡本太郎。
万国博覧会のシンボルタワーの制作の合間を縫って、メキシコに渡り、完成させた作品だった。
しかし、そのホテルは経営悪化により人手に渡り、「HIROSHIMA NAGASAKI」、いや、実に32年後に「明日の神話」という新しい名を冠して甦るその巨大壁画も、いったん行方不明となるのだった。
*
1月2日、皇居で行われた一般参賀。
バルコニーにいた昭和天皇の足下近くに、パチンコ玉が3発続けて、飛んできた。
「ヤマザキ、天皇をピストルで撃て!」
昭和天皇から15メートル先で、声が響いた。
ゴムパチンコを構えた男が、そこにいた・・・。
*
東京大学本郷キャンパスは、新春から揺れていた。
ベトナム反戦、安保闘争、インターン闘争、授業料値上げ反対、学園民主化・・・。
前年の6月から続く学内闘争は、安田講堂をバリケード封鎖し、ひとつの城をつくりあげた。
1月18日から19日にかけての2日間。
全共闘(全学共闘会議)と新左翼の学生によって占拠されたキャンパスを、警視庁が突入、600人以上の大捕物となった。
敵に催涙弾を撃ちながら城攻めする機動隊に対し、全共闘は屋上から火炎瓶や石を投げ、硫酸やガソリンも散布するという、戦争状態の末、双方、多くの学生と警官が重軽傷を負った。
*
街には、フォーク・クルセダーズを解散した、はしだのりひこが新たに結成したグループ、「はしだのりひことシューベルツ」の歌が流れ出した。
北山修が作詞した「風」は、こう歌う。
何かを求めて振り返っても
そこにはただ風が吹いているだけ
振り返らずただ一人 一歩ずつ
振り返らず泣かないで歩くんだ
ボブ・ディランが「風に吹かれて」で歌ったその風は、誰の背中にも吹いていたし、そして誰もがその風そのものだった。
*
高石友也事務所は、URC(アングラ・レコード・クラブ)を設立。
日本で初めての、インディーズのレコード・レーベルだ。
だが、エンケンこと遠藤賢司は、最初、東芝エキスプレスからデビューしている。
「ほんとだよ / 猫が眠ってる」。
フォークキャンプや高石事務所で知古を得た人々、早川義夫、木田高介、西岡たかし、加藤和彦といった面々がレコーディングに参加し、それぞれシタールやタブラなどを演奏している。
エンケンは、その初期から常にあらゆる音楽的要素を含んだ世界を展開していた。
ボブ・ディランの「ライク・ア・ローリングストーン」に影響を受けて歌い始めたエンケンだが、同時に歌謡曲や既存の芸能の影響や感動も、同じ単位で語るところが素敵だ。
ある意味、「〜であるべき」「〜ねばならない」「〜派」といった原理主義的側面の多かった60年代末から、遠藤賢司は何かと何かを差別しないことで、すでに純音楽家だった。
純音楽家とはエンケンの代名詞だが、フォークやロックや何やらとカテゴライズされずに音楽を旅する加藤和彦や西岡たかしらも、同じように純音楽家と言えるはずだ。
フォークかロックかとか、オリジナルな音楽か既存の歌謡曲かとか、そうした思想的対決が個人の中や音楽界全体でスパークしていた時代に、遠藤賢司はフォークもロックも歌謡曲も何も差別せず、自分に影響を与えたすべてに感謝し、また自らのライバルとした。
それによって、結果、生み出されるのは、ほんとうに自分の内面にあるものだったのだ。
*
高石事務所が設立したURCは、最初、市販ではなく、会員に配布する形をとっていた。
激動の中心部から生み出される歌たちが、日本中にいるアンテナ立てた若者のところに届くのである。
第1回会員配付は、「高田渡 / 五つの赤い風船」。
A面が高田渡、B面が五つの赤い風船というカップリング盤である。
ぼそぼそと小さな声で喋り、美しく激しいピッキングでギターを鳴らし、明治の壮士演歌をフォークブルーズに乗せて歌い継ぐ。
そこにいる歌い手は確かに若者のはずだが、もう人生の様々なことを体験してきたような面持ちだ。
初期の高田渡は、その鋭いユーモアで、皮肉たっぷりに現世を風刺する。
添田唖蝉坊、添田さつきの遺伝子、ウディ・ガスリー、ピート・シーガーの遺伝子、そして父、高田豊の遺伝子。
幼い頃から社会の底辺を見て育った渡にとって、時代だの世代なんてものはただの言い訳にしか聞こえなかったろう。
アルバムは、いきなりハイテンションのギターで始まる。
しかし、その高田渡の歌い方は、早口なのに朴訥としている不思議。
さあさあ 事だよ事だよ
お金がないない お金がない
机のひき出し 洋服ダンス
下駄箱の中 トイレの中まで
さがしたけれど どうしてもないよ
・・・・
夢でひろった お金がない!
西岡たかし率いるグループ、五つの赤い風船は、シンプルな高田渡の世界とは真逆とも言える、実験的要素の強い音楽集団だ。
西岡のつくり出す叙情的な詩世界と胸を打つメロディ、職人が集まってひとつの作品を紡ぎだすような工房のような雰囲気、そしてボーカリスト藤原秀子の歌声。
「高田渡 / 五つの赤い風船」は、胸に秘めたソウルは同じでも、やり方考え方が全然違う2組をカップリングした、ひとつの夜明けを感じさせるアルバムだ。
*
新宿駅西口地下に、フォークゲリラと称する連中が現れ出した。
社会を風刺し権力を裸にするフォークソングは、ベトナム戦争反対をはじめとする市民運動や学生運動の武器となった。
うたが、目的でなく方法として、道具としてそこにあった。
その歌の紡ぎだすイメージに思いを巡らすのではなく、あくまで反権力の武器として、フォークソング、関西フォークは使われた。
高石友也や岡林信康や中川五郎の歌が、歌い手を離れて、運動家のプラカードやゲバ棒やヘルメットと等しい装備品のひとつになっていた。
中川五郎は「ベトナムに平和を!連合」(べ平連)とコミットしたが、一方でたとえば高田渡は、「新宿フォークゲリラ諸君を語る」という歌をつくり、批判した。
高田には、大勢で群れて、歌を道具にし、騒いでいるような連中は、たとえそれが正義のためだろうと、エリートやインテリのお坊ちゃんお嬢さんにしか見えなかったのかもしれない。
音楽(芸術)と、運動(革命)。
この辺りのバランス感覚や、歌それ自体についての思想論は、いまもって答えを出さないまま残っている。
もっとも、2011年の日本の運動シーンで流れているのは、フォークではなくヒップホップだが・・・。
*
3月20日、大阪で「あんぐら音楽祭」。
出演は、高石友也、ジャックス、遠藤賢司、岡林信康、中川五郎、高田渡、五つの赤い風船、六文銭、加藤和彦、はしだのりひことシューベルツ。
乱暴な言い方だが、ロックと呼ばれた人々が「外」に向かっているとき、フォークと呼ばれた人々は「内」に向かっている。
主観の意見をどれだけパワーにできるか闘うロック、客観の視点をどれだけイメージできるか模索するフォーク。
ハンマーを持って壁を壊すロック、そのハンマーを持って壁を壊している自分に対して「なぜ、壊すのか」と自問自答してみせるフォーク。
もちろん、物事の本質はあらゆる思想や行動のあいだに閃くものであり、ジャンルやカテゴリーにすっぽりハマるものではないが、60年代末から70年代始めにかけて、「外」と「内」どちらにも個や時代のエネルギーが轟いていたことは確かだ。
たとえば岡林信康は、「それで自由になったのかい」と歌った。
早川義夫は、「かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう」と歌った。
URC出身のシンガーたちの作品は、その歌の題名が、もはや完成された一編の詩であり、また強烈なキャッチコピーだ。
なぜ、19、20歳の者たちが、「それで自由になったのかい」と疑問を突きつけ、「かっこいいことはかっこ悪い」と言ってみせたりしたのか。
革命家たちが権力に対して拳を上げるとき、ロックンローラーはその拳の先を見つめ、フォークシンガーはその拳を見つめていた。
*
URCの第2回会員配付は、「六文銭/中川五郎」、岡林信康「くそくらえ節」、高田渡「大ダイジェスト版三億円強奪事件の唄」の3枚。
これは、アルバム1枚とシングル2枚と言っていいだろうか。
PPMフォロワーズとしてフォーク黎明期から活躍している小室等のグループ「六文銭」と、前年に高石友也によってアレンジされヒットした「受験生ブルース」の作者である中川五郎。
21世紀のいまも活動を続ける、フォークの立役者的2人だ。
高田渡の「大ダイジェスト版三億円強奪事件の唄」は、前年の1968年に起こった、いわゆる三億円事件を、事細かに解説し、実況する歌だ。
途中、替え歌が入ったり、ほかの演者が登場したりと、面白いコミックソングになっている。
初期の高田は、「自衛隊に入ろう」「東京フォークゲリラ諸君を語る」「大ダイジェスト版三億円強奪事件の唄」と、時事ネタがいくつかある。
これはもちろん、添田唖蝉坊ら明治の演歌師の影響だろう。
4月には、エレックレコードが発足された。URCの設立からわずか2ヶ月ほど。
フォークソングは金になる。メジャーなフォーク、マイナーなフォーク、様々な歌が交差しながら、フォークは市民権を得た。もっとも、民衆の歌という意味であるフォークソングが、市民権を得るなんていうのは、おかしな言い回しだ。
ザ・フォーク・クルセダーズを解散した加藤和彦は、「僕のおもちゃ箱」でソロアルバムデビュー。
はしだのりひことシューベルツは、シングル「さすらい人の子守唄/夕陽よおやすみ」、そしてアルバム「未完成」をリリース。
五つの赤い風船は、URCとは別にメジャー・レーベルから「恋は風にのって」をリリース。
様々な方向に、様々な手段で、歌が生まれては彗星のように跳んでいく。
フォークソングがポップスになり得た瞬間に、1969年という時代が腰掛けていた。
*
URC第3回配付は、『休みの国 / 岡林信康リサイタル』。
「休みの国」は、カイゾクこと高橋照幸によるバンド。
この岡林とのカップリング盤は、ジャックスの合宿に運転手として参加したカイゾクが、休憩時間などにジャックスのメンバーとともに演奏したものが収録されている。
休みの国は、カイゾクを中心に、メンバーを替え続け、いまも超不定期ながら活動している。
この高橋カイゾクという人は船が大好きで、人生のほとんどを海に思いを馳せており、自ら船を設計し建造したりする。
で、ときどき思い出したかのように「休みの国」をそのときそのときの新たなメンバーで結成し、音楽活動を始める不思議な人だ。
*
予備校に侵入し、金を盗もうとしていた男が日本警備保障の警備員に発見され、銃を発砲し、逃走。
数時間後、警視庁の緊急配備によって逮捕されたのは、前年の1968年に4人を射殺した、永山則夫だった。
不幸な環境で育った永山は、連続射殺魔として世間に知られ、そして獄中で詩人となる。美しい言葉を紡ぐ作家となる。
あまり知られていないことだが、1997年に死刑が執行された永山は、晩年、著書の印税を遺族に送ったり、ペルーの恵まれない子供たちに寄付したりしている。
殺人を犯し投獄されたが、古いフォークソングやブルースを多く知っていることから恩赦を受けた、あのレッドベリを思い出さずにはいられない。
永山則夫の詩も、レッドベリの曲も、数年後、高田渡のレパートリーに加えられることになる。
この世の様々な闇の中に光るきらめきを、高田渡は見逃さず、そのギターの弦の音に込め、歌になることにおいて、すべてはひとつになっていく。
*
7月19日、新宿西口地下広場のフォーク集会を、機動隊が逆占拠。集会禁止令は5月に発令されていた。
「ここは広場ではない。通路である」と警察が言い、フォーク集会およびゲリラは解散した。
いまも新宿駅の西口地下広場は存在するが、確かに広場と言われれば広場だし、通路と思えば通路である。
再び通常の駅の一部となった新宿西口地下広場。
フォークゲリラたちが歌った、あの関西フォークのレパートリー、反戦と反権力の歌たちは、どこへ響いて響いて消えゆくのか。
そこに集っていた無数の若者たちは、ひとりひとり、それぞれの家や学校や職場に戻っていったのだろうか。
そのとき、歌は、どこへ行ったのか。
*
8月、URCの第4回配付は、『世界のプロテスト・ソング』。これが最後の会員配布となり、以降は市販になる。
同月、岡林信康のファーストアルバム「わたしを断罪せよ」、五つの赤い風船の「おとぎばなし」がリリース。
「今日を越えて」で始まり、「友よ」で終わる岡林の世界は、とてもシンプルでまっすぐだ。
当時、岡林はほんとうに「友よ」と思いを投げかけていた。時代の夜明けを信じていた。そしてそれ故にカリスマとなり、重圧がのしかかることにもなった。
しかし、ここに流れる岡林のメッセージは、その声のかわいらしさも相まって、純粋だ。
「おとぎばなし」は、「まるで洪水のように」や「ボクは風」といった名曲が収録されたアルバムだが、この盤はほとんどCDで再発されていない。残念。
*
「ヤマザキ、天皇をピストルで撃て!」
そう叫んだ男はもう1発、標的を狙撃しようとした。
しかし、その簡易な銃弾は、やはりバルコニー近くに当たっただけだった。
取り押さえられ連行された男は、奥崎謙三と名乗った。
その掌には、手作りのゴムパチンコ。
ヤマザキとは、戦争で死んだ友の名だった。
奥崎は、そのキャラクターの強引さや、殺人罪といった暴力的側面は問題だが、しかし時代が戦争をすっかり忘れたふりをしても、ひとり、天皇の戦争責任を訴えていたのだ。
戦後もすでに、14年の月日を過ごしていた。
遥かな宇宙空間に、岡林信康の「わたしを断罪せよ」が聴こえてきた。
「わたし」とは、誰のことか。
ギター抱えた岡林信康、パチンコ撃った奥崎謙三、標的になった昭和天皇、戦死したヤマザキ、連続射殺魔となった永山則夫、火炎瓶投げる東大全共闘、催涙弾撃つ機動隊、三億円強奪事件の犯人、美濃部東京都知事、高石友也、中川五郎、高田渡、遠藤賢司、ジョン・レノン、ミック・ジャガー、内田裕也、岡本太郎、ベトナム国民、アメリカ軍人、時を越えてこれを書いている私、これを読んでいるあなた、時代の一瞬一瞬に込められた紛れもない事実の連鎖、すべてはいまであり、いまがすべて、わたしを断罪せよ、わたしを断罪せよ・・・それで自由になったのかい。
*
ヒッピーと大学紛争とベトナム反戦とチクロとセブンスターと東名高速の1969年。
3月12日には、首都圏に大雪が降った。
由紀さおりがスキャットを口ずさみ、いしだあゆみが横浜の慕情を歌ってた。
長崎はいつも雨だったし、キングトーンズはドゥワップし、3歩進んで2歩下がりながら懸命にそれぞれの人生を生きた。
映画館のスクリーンには寅さんのうしろ姿、ブラウン管には東野英治郎の水戸黄門。
クレージーキャッツは、変わらず人気者だった。
・・・レコードをひっくり返して、B面へ続く!