「まさかこんな所にメメクラゲがいるとは思わなかった
ぼくはたまたまこの海辺に泳ぎに来て
メメクラゲに左腕を噛まれてしまったのだ
当然静脈は切断された
真赤な血がとめどもなく流れだした
ぼくは出血多量で死ぬかもしれない
一刻も速く医者へ行かなければならないのだ」
(つげ義春「ねじ式」)
1968年、昭和43年。
ベトナム戦争は続き、虐殺事件が立て続けに起こった。
日本では金嬉老が静岡の旅館に立てこもり、原子力空母エンタープライズの寄港を阻止する闘争が起こり、北海道の美唄炭鉱ではガス爆発、東京大学は紛争にまみれた。
アメリカではマーティン・ルーサー・キングが、そしてジョン・F・ケネディが暗殺された。
アポロが月から地球の写真を撮った。
私たち人類は、宇宙に手が届きそうな錯覚をおぼえながら、同時にこの青い惑星の上で相変わらず殺し合いを続けていた。(犠牲になるのはいつも弱者)
死神にまとわりつかれた阿呆たちの見る未来はどこに?
東名高速道路が開通、自動車はブーブーと列島を走りまくり、大気汚染防止法と騒音規制法が施行された。
小笠原諸島は日本に復帰、アメリカ統治の琉球は初めて行政主席の選挙が行われた。
岡本喜八監督の「肉弾」は、私が大好きな映画だ。寺田農演じる主人公の「あいつ」が、大谷直子の「ネズミ」、笠置衆の古本屋、三戸部スエのモンペのおばさん、上官の田中邦衛、船長の伊藤雄之助らと出会っていき、最後のあのドラム缶、方程式とネズミとドラム缶、寺田農が海に浮かんでいる。戦争の愚かさ、滑稽さ。
しかし、スタンリー・キューブリックは「2001年宇宙の旅」なのである。岡本喜八の言葉と色(モノクロだが)の饒舌さに対して、宇宙、ただ無言の銀河である。喜びも悲しみも超えた、その真っ黒な宇宙は、ベトナム戦争終わらない60年代後半の産物だ。そしてあらゆるアートが世界中でひしめいた時代のしるし。
週刊少年ジャンプが創刊され、大衆は「ハレンチ天国」に熱中した。
一部の者は、月刊漫画ガロに掲載された、つげ義春の「ねじ式」に衝撃を受けた。
その間を取り持つかのように、「ゲゲゲの鬼太郎」はテレビアニメ化された。
しかし、水木しげるはこの頃、経済成長していくこの国の変貌を見ながら、自分が描いてきたこと、すなわち、目に見えないものこそ大切であるというメッセージは間違っていたのだろうかと弱気にもなっていた。
そんな1968年、フォークシンガーやロックミュージシャンたちもまた、歌うことで歴史に新しい価値観をぶつけていた。
「都の人はスモッグのような心で
小さな箱(家)から大きな箱(ビル)へ
せかせかと通うだけで一生は終わる」
(水木しげる「まぼろし旅行記」)
2月、フォーク・クルセダーズの「イムジン河」は、発売中止が発表された。
朝鮮総連が求めたのは、原詞に忠実に訳すことと、北朝鮮の民謡であることをクレジットすること。
確かに、松山猛による2番と3番は、原詞とまったく違う。
しかし当時、日本と北朝鮮、いや、朝鮮民主主義共和国には国交がなく、国名のクレジットは躊躇われた。
そのほか、いろいろな方面からの圧力があり、「イムジン河」は発売禁止となった。
その一週間後に発売されたのが、高石友也の「受験生ブルース」だった。
中川五郎や岡林信康といった年下の仲間たちと歌の旅をするのと同時に、高石友也はビクター専属のプロミュージシャンでもあった。
1966年の「かごの鳥ブルース」でデビューしたのち、67年には「想い出の赤いヤッケ」をリリースしている。
「受験生ブルース」は本来、中川五郎の持ち歌であり、高石はこれを自分流につくり直し、リリースした。中川の歌が高石によってメジャーレーベルから世間に知られる。不思議な現象である。
しかし、これはフォークソングというもの、ひいては歌というものの本来の姿である。誰かがつくり、それを誰が歌ってもいいし、どうつくり直してもいい。そうしたフォークソングイズムにさらに、高石と秦政明の戦略的なやり方がプラスされ、フォーク革命は着々と進んでいたと言える。
ところで、この「受験生ブルース」のジャケットは、園山俊二による絵である。その頃の園山俊二といえば、「がんばれドンベ」のほか、1作目の「ギャートルズ」を週刊漫画サンデーに連載していた。
ギャートルズの由来は、もちろんビートルズ。「ギャートルズ」には、「この話 はヘイジュードを聞きながら読んでください」と書かれたコマがある。
「イムジン河」のかわりにフォークルがリリースしたのが、「悲しくてやりきれない」。わずか1ヶ月後の発売だった。
「加藤和彦が『イムジン河』のレコードを逆回転したメロディに・・・」という逸話は間違いで、「逆回転させて思いついたメロディ」というのがほんとう。
それを大詩人サトウハチローのところに持っていくと、ちゃんとひとつの音に言葉がのっていて、その見事さに加藤たちは驚いたという。
言わばこれは、モダンフォークや歌謡フォークとはまた違う、別の意味でのフォークソングと歌謡曲の融合だろう。
また、彼らは映画にもなった。時代の寵児フォークルを主役にした映画をつくろうという動きが出たのだ。
フォークルのメンバーは、監督に大島渚を選んだ。そうして出来たのが、映画「帰って来たヨッパライ」である。
主人公は、加藤和彦、北山修、端田宜彦演じる、3人の大学生。
卒業旅行の最中、日本海で海水浴をしていると、何者かに着ているものを盗まれてしまう。
しかたがないので、3人はかわりに脱ぎ捨てられていた韓国陸軍の軍服を着る。すると韓国からの密航者として警察に追われてしまう。
軍服の持ち主であるベトナム戦争への徴兵から逃げて来た韓国陸軍兵長にも追われることになり・・・というの物語の前半。
後半は、前半と同じストーリーが繰り広げられる。しかし、今度の3人は何が起こるかわかっていて、もうひとつの物語を演じていく・・・。
奇才・大島渚の怪作。大島組の常連、佐藤慶も登場する。
ウディ・ガスリーがこの世にいない、最初の年。
彼の子供たちは、どうしている? アメリカのフォーク界も覗いてみよう。
ピート・シーガーは、環境保護団体などの市民運動に深くコミットしながら歌い続けていた。「Wimoweh and Other Songs of Freedom and Protest」をフォークウェイズレコードからリリース。
ランブリン・ジャック・エリオットは「Young Brigham」を、ジョーン・バエズは「Baptism: A Journey Through Our Time」と「Any Day Now」をリリース。
ボブ・ディランは、この年はレコードを出していない。
デイブ平尾のザ・ゴールデン・カップスは、ファーストアルバム「ゴールデン・カップス・アルバム」をリリース。
ロックファンは、グループサウンズは歌謡曲、芸能界っぽいと思っていた。しかし、ゴールデン・カップスだけは少し別だった。
少年期の忌野清志郎が熱中したのはカップスだし、加藤和彦もカップスだけはロックと認識していた。
こういう場合のロックとか何とかいうのは、決して音楽様式や形態のことではなく、姿勢の問題である。姿勢、或いは思想。
それは、「ロック」だけでなく「フォーク」もそうだし、「ブルーズ」もそうだ。
モダン・フォークが「こざっぱりさせたフォーク」だったように、GSも「芸能界っぽいロック」だった。
歌謡曲的なものに対抗する何かを、フォークやロックのディープな場所で闘っている者たちは持っていた。だから当時は、必要以上に歌謡曲を敵視し、ほんとうのロックとかほんとうのフォークとかを模索する向きがあったのだ。
しかし、音楽はすべて音楽だし、歌謡曲だろうとフォークだろうとロックだろうと、聴いている人が楽しめればいいっちゃあいいのである。
ザ・タイガースは、この年、後楽園スタジアムでコンサートを開催。これが日本初のスタジアム公演となった。
タイガースは、ジュリーこと沢田研二がボーカル、ほかにベースでバンドリーダーに岸部一徳などがいた。いまや素晴らしい俳優の二人、そういえばテンプターズは萩原健一だし、GS以前のスパイダースにはマチャアキに井上順にムッシュかまやつと、う〜ん、やっぱり、ザ・芸能界もいい!
芸能界っぽさと、ルーツミュージック原理主義っぽいのと、どっちもあっていいんだ。それらが渾然一体となるのが、この国の面白いところだ。
ちなみに、タイガースのメンバーは全員、スパイダースのファンクラブに入っており、また彼らをワタナベプロに誘ったのは内田裕也だった。
ローリング・ストーンズは、「ビガーズ・バンケット」をリリースし、1曲目の「悪魔を憐れむ歌」は社会的問題となった。
何故、この連載でビートルズとトローリング・ストーンズも一緒に追っているのか?
ブルーズやジャズについては書かないのに、何故、「アメリカのフォーク」と「イギリスのロック」を書くのか?
それにはうまく答えることはできないのだが、日本のフォーク&ロックの歴史を辿るために、こうしたバランスがいいのではないかと何となく思ったのだ。
「ブリティッシュ・インヴェイジョン」という言葉がある。これは、「フォーク・リバイバル」と同じくらい重要である。
1960年代、ビートルズやストーンズが、アメリカの黒人音楽に影響された曲を発表していった。そこにはブルーズが流れていた。はじけるリズムがあった。
エルビス・プレスリーの人気が衰退した60年代アメリカにおいて、白人と黒人を結びつけるロックやR&Bのスターの数は少なかった。そこにアメリカにやって来たのが、イギリスの連中だった。アメリカのロックスターとは違う彼らの魅力に、若者たちは熱中した。
このブームは、フォークソングにも影響し、同時にボブ・ディランの存在もあり、フォークとロックは容易に結びついていった。だからロックは、フォークのように社会に抗議する歌を生んでいった。
フォークとロックは、ブルーズのもとにひとつになっていった。ただし、これはアメリカの話であり、日本はこれからが大変・・・。
「ビガーズ・バンケット」は、「乞食の晩餐会」の意。
アメリカでは、バッファロー・スプリングフィールドが解散した。
1月に再びブルース・パーマーが麻薬でカナダに強制送還。
ジム・メッシーナを加えての新体勢となるも、4月にスティーブン・スティルスらも薬物問題が発覚。
5月に解散コンサートが開かれ、わずか2年間の活動は幕を閉じる。
しかし、バッファロー・スプリングフィールドの音楽性は、日本の若者たちに引き継がれ、まったく新しいものとして生まれ変わる。
それは、もう少し先のこと。
解散後、それまでのレコーディングされた曲を集めて、アルバム「ラスト・タイム・アラウンド」をリリース。
アルバムが3つであること、そして最後のアルバムはメンバーそれぞれの作品が集められた傾向が強いこと。この2年後に東京で芽生える日本語ロックの代表的バンドとの類似点である。
やっぱり三段落ちが、はっぴいえんど・・・?
3月には、大阪で「アンダーグラウンド音楽祭」というコンサートが催された。
これには、フォークル、高石友也、中川五郎、ジャックス、五つの赤い風船、小森豪人、メディテーション(真崎義博、金延幸子、内田千鶴子ほか)などが登場し、岡林信康も飛び入り出演。
岡林や風船にとっては、本格的な活動の始まりとなった。
そして8月、「第3回京都フォークキャンプ」が開かれた。
高石、中川、岡林、風船といった関西勢とともに、東京勢も合流した。
PPMフォロワーズを解散した小室等の、六文銭。
それから、東京のフォーク集団「アゴラ」に属していた、高田渡、遠藤賢司、南正人ほか。
メジャーなレコード会社に籍を置くフォーク・クルセダーズと高石友也、関西の若きシンガー中川五郎に岡林信康、音楽的要素の強い西岡たかし率いる五つの赤い風船、東京からやって来た愛すべき自由人たち・高田渡に遠藤賢司に南正人・・・。
様々な面子が混ざり合い、ほんとうのフォークブームがいままさに起ころうとしていた。
また、フォークキャンプに出演する連中で、「フォークキャンパーズ」というグループがあった。
これは、正式なメンバー体勢ではなく、流動的で、あるときは1人、あるときは100人という、そこにいる人間が集まり歌う集団の名称だった。
このグループ、3月には「女の子は強い/誰かがどこかで」をテイチクからリリースしている。高石友也の弟子を自称するリーダー格の藤村直樹が、このレコーディングに参加していたのかどうかは定かではない。
それにしても、関西フォークは、その過激さから発売中止や放送禁止が多い。
5月に「くそくらえ節」をリリースした岡林信康だったが、発売禁止に。
岡林は、10月に「山谷ブルース」で改めてデビュー。
ジャックスは、早川義夫や木田高介らのバンドで、すでにソロ・コンサートやテレビ出演などを果たしていた。
3月に「からっぽの世界」でレコードデビュー。
続いて、5月に「マリアンヌ」、9月に「からっぽの世界」、10月に「この道」と、シングルを連発する。レコード会社は、フォークルと同じ東芝だ。
その人間のココロの暗い部分を震えた声で歌う、何か特権的とも言うべき陰鬱さ。
ロックの黎明期を代表するバンドのひとつだが、高石事務所に所属し、フォークの面々と行動をともにしたことは、歴史的にとても重要だ。これは、のちのはっぴいえんどにも言える。
9月には、ファースト・アルバム「ジャックスの世界」がリリースされた。
社会や世界をメッタ打ちに風刺し、毒と笑いで突く岡林。
悩み多き若者の内面を情念たっぷりに歌う、ジャックス。
岡林からジャックスまで、様々な音楽家が、高石友也が振る旗のもとに同居していたと言える。
そして第3回フォークキャンプで、最も聴衆に衝撃を与えたのは、高田渡だろう。
そう、「自衛隊に入ろう」だ。
逆説でもって痛烈に風刺する歌。
元共産党員の日雇い労働者、詩人・高田豊を父に持ち、幼い頃から貧困と放浪を経験した渡だからこそ、こういう発想が自然に出てくる。
これを聴いて、実際に自衛隊に入ったという者もいた。
これを聴いて、自衛隊が喜んで渡に連絡をしてきた。
あのニヒルな無表情で、高田渡は呆れていたに違いない。
当時、自衛隊への勧誘が、街中などで頻繁に行われていた。ふらふらしている若者に、積極的に防衛庁は声をかけていた。
いまも様々な雑居ビルに自衛官募集の支部があったり、街の掲示板に貼り紙があるが・・・。
ああ、でもいままた、東日本大震災での仕事ぶりをテレビで観て、自衛官に純粋に憧れる子供たちも多いのだと思う。
しかし、高田渡は歌い貫く。
それは人を殺すことだ、それは戦争に参加することなんだと。
どんなに時代が変わっても、彼はすべての軍隊に反対していたと思う。
だけど、高田渡は、それをストレートには決して訴えない。
メッセージソングなんかにしないのは、彼の一級の照れである。
「皆さん方の中に 自衛隊に入りたい人はいませんか
一旗揚げたい人はいませんか 自衛隊じゃ人材もとめてます」
フォーク・クルセダーズも「悲しくてやりきれない」に続き、7月に「水虫の唄」、11月には「ゲゲゲの鬼太郎」のカバー、同日に「さすらいのヨッパライ」とシングルを連発。
カップリングの曲も、「戦争は知らない」だったり、童謡の「やぎさんゆうびん」だったりと、気に入った歌は何でも持ち歌にしてしまう! これぞフォークイズム!!
同時に「コブのない駱駝」のような、北山修の紡ぐ、風刺のこもった不思議な音楽世界も繰り広げられる。
7月には、アルバム「紀元弐阡年」をリリースした。
これはフォークであり、ロックであり、またサイケデリックでもあり・・・。
とにかく、遊び心満載で、音楽的に斬新な名盤である。
当時としては破格の製作費だったという。
同じく7月、「当世今様民謡大温集会(はれんち・りさいたる)」なるコンサートを開催。
口上あり、コントありのサイコーのライブに仕上がった。
そうして唯一のオリジナルアルバムと素晴らしいライブ盤を残して、フォークルは10月、「さよならコンサート」をもって解散する。
約束通りの1年間、3人は「音楽」、そして「芸能」というものの面白さを凝縮して世間に見せつけ、姿を消した。
フォークルは、自由だった。
もっとも、関西フォーク、アングラフォークと呼ばれた連中は、みな自由だった。
芸能界という世界にもとより憧れていないし、ただ面白いことがしたいとか、或いは戦争や差別に抗議したいとか、きれいなメロディが浮かんだから歌いたいとか、そういうことだったのだから。
そうしたテッテ的(!)なアマチュアイズムを忘れぬまま、ザ・フォーク・クルセダーズは「芸能人」となった。
何てったって、マルベル堂のブロマイドが売り上げ14位だったというんだから。
映画に主演し、コント番組に出演し、彼らは束の間の芸能人だった。
誰よりも、どんな芸能人よりも、自由だった。
タイガースの瞳みのるが東京に出ていくとき、「儲けるまでやめへん」と言った。
それを見て、北山修は、「自分たちの方が自由だ」と思った。
実際、人気絶頂の中で、ハイやめた!と解散できるんだから。それは、自由だから。
で、すぐにみんな別々で出てくる。共演もしょっちゅうする。それも、自由。
フォークル解散ライブに、端田宜彦はすでに新しいバンドを引き連れて歌ってた。自由だから。何でもありだから。
全部、自分で決めていい。
ザ・フォーク・クルセダーズは、どんなフォークシンガーよりも、どんなロックバンドよりも、どんなアイドルやスターよりも、自由だった。
ぼくは、北山修のこのギャグが、ナンセンスで大好きだ。
「3曲目の前に、2曲目をお送りします」
きょうのエンディングテーマは、2002年に新結成したときの「紀元弐阡年」。
読んでくれて、ありがとう!
(いろんな書籍、ホームページ、テレビでの発言などを参考にしています)
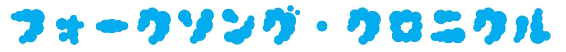
![肉弾 [DVD] 肉弾 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21KZNFJ74CL._SL160_.jpg)
![2001年宇宙の旅 [DVD] 2001年宇宙の旅 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21EQ1YERZWL._SL160_.jpg)


![帰って来たヨッパライ [DVD] 帰って来たヨッパライ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31C2TYXDFCL._SL160_.jpg)











