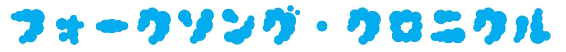1967年、昭和42年、秋。
あるホテルのフロントに、18歳になっていた高田渡がいた。
父を亡くし、いったんは佐賀の親戚の家に預けられたものの、すぐに東京に戻り、新宿は若松町のアパートで暮らしていた渡。
しばらくすると、向こうのほうから、優しい顔をした背の高い男が現れた・・・。
ツイッギーのミニスカート、葉巻煙草のパロマ、森永製菓のチョコボール・・・。
遥か中東の地では、イスラエルがアラブ連合に戦闘勝利し、領地を拡大。
ベトナムではトンキン湾で、アメリカ海軍空母フォレスタルが爆発。
中国の文化大革命に、三島由紀夫や川端康成たち作家陣が反対声明。
高度経済成長の哀れな犠牲、四日市ぜんそくの被害者たちが提訴。
水木しげるの「墓場の鬼太郎」にも登場する血液銀行が、売血をやめた。
詩人、歌人、劇作家として活躍していた寺山修司は、「演劇実験室 天井桟敷」を旗揚げした。1月1日、元日のことである。
この年、「青森県のせむし男」を皮切りに、「大山デブ子の犯罪」、「毛皮のマリー」と、次々に問題作を世に打ち出した。
一方、1965年に旗揚げされた唐十郎たちの状況劇場は、新宿の花園神社境内で紅テントを建てる。21世紀のいまも続く、花園神社の紅テントだ!
しかし、演目の「腰巻きお仙」という題が、神社側からクレームがあり、しかたなく唐は「月笛お仙」と改題するが、何日か経つとすぐに「腰巻き」に戻したというからオモシロイ。
演劇の世界でアンダーグラウンドなところから新しい潮流が巻き起こるのと同時に、音楽の世界も劇的な動きを生む。
アマチュアとして活躍していたフォーク・クルセイダーズは、加藤和彦、北山修、平沼義男の3人になっていた。
4月、渋谷公会堂での「シング・アウト・東京」というコンサートにて、初めて「イムジン河」を披露。
イムジン河は、朝鮮半島に流れる川。
朝鮮民主主義共和国と大韓民国の間を流れる川である。
話は、加藤と北山の盟友である松本猛の、中学生時代にさかのぼる。
京都では、日本人の生徒たちと朝鮮学校の生徒たちとの喧嘩が多く、松山猛もその渦中にいた。
彼はある日、朝鮮学校にサッカーの試合申し込みに行く。そのときに校舎で聴いたのが、朝鮮民謡の「臨津江」だった。
きっと、松山は純粋にただ、美しい曲だと思ったのだ。
夕暮れどきの九条大橋。トランペットの音が響いている。
いつのまにか音色は、別の音色と重なり、ひとつの音楽となって空気中に融けていった。
サックスの音だ。トランペットとサックスが鴨川の水の流れの上に踊っている。
トランペットを吹いていたのは、松山猛。
サックスを吹いていたのは、文光珠という朝鮮学校の生徒だった。
2人は友達になった。松山は、「臨津江」の歌を教わった。日本語に訳したものは、文のお姉さんが書いてくれた。
それから数年後、加藤和彦に口伝えで歌を教え、できあがったのが「イムジン河」。
松山が文姉弟に教わったのは、1番だけ。それじゃああんまり短いので、松山が2番と3番を新しく書き足した。
こうして、フォーク・クルセイダーズの「イムジン河」はできあがった。
このあたりの話は、井筒和幸監督の映画「パッチギ!」のストーリーの元になっている。
京都で活躍したアマチュアのフォーク・グループには、フォーク・クルセイダーズのほかに、ドゥーディー・ランブラーズ、グリーディー・グリーメン、モダーン・ルーツ・シンガーズ、それから大塚孝彦がいた。
この「大塚孝彦とそのグループ」が自主制作したアルバム「ファースト&ラスト」に、フォークルの面々は参加している。
これがきっかけで、「あ、つくれるんだ」と思い、「ハレンチ」の制作に進めたという。
大塚孝彦は、京都のフォーク界の重鎮的存在で、「竹田の子守唄」や「風に吹かれて」などの曲が吹き込まれた「ファースト&ラスト」のジャケットもまた、松山猛の作画である。
7月末、京都の神護寺で、2日間にわたって「第1回関西フォークキャンプ」が開かれる。「フォークキャンプ」は「フォークジャンボリー」の前身のようなコンサートで、4回行われている。
第1回フォークキャンプの出演者は、高石友也、中川五郎、フォーク・クルセイダーズほか。
いわゆる音楽だけのコンサートではなくて、歌と討論の集まりで、何から何まで手づくり、まさにDIYの催しだった。
マネージャーの秦政明とともに、日本中にフォークソングを広めていた高石友也。労音や反戦集会を回り歌い巡る高石の旅は、そのまま日本におけるフォークソングの最初の「種まき」だったかもしれない。
高石と秦という2人の農民が、日本という畑にフォークソングの種をまき続けた。その種は、アメリカから運ばれてきたものだった。ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、ボブ・ディラン、ジョーン・バエズ、マルビナ・レイノルズ・・・。2人にとって、とてつもない生き甲斐を感じた時代だったのではないだろうか。
「高石友也リサイタル」を大阪で開催、そして第1回フォークキャンプへと流れていく。秦政明は高石事務所をつくり、マネージメントやプロデュースはますます本格的なものとなる。同時期にフォークシンガーとして歌い出した若者たちが、2人のもとに集まってゆく。
高校3年生だった中川五郎は、3月にベトナム反戦集会に行ったときに、高石友也を見る。ぼくもあなたのように歌をつくって歌っている、そう高石に話しかけ、中川は高石のフォークの種まきの旅に同行した。
また岡林信康も、高石と出会う。
さて、第1回フォーク・キャンプが終わり、フォーク・クルセイダーズは、解散記念としてレコードを製作。自主製作盤「ハレンチ」だ。
緑と赤の印象的なジャケットは、松山猛によるもの。加藤和彦のような若者とガイコツが並んでいる不思議な絵。
23万円かけて300枚つくった「ハレンチ」、これがラジオで話題になる!!
アルバムに収録されている曲は、「イムジン河」や「ヨルダン河」「そうらん節」「コキリコの唄」といった民謡、「ひょっこりひょうたん島」のテーマや「帰ってきたヨッパライ」といった楽しいコミックソング、「グァンタナメラ」のようなアメリカン・フォークのカバーと、多彩な内容となっている。
まじめなことをやっているように見せておいて、お笑いがちょこちょこと入ってくるという、フォークルのやり口は、初期の頃から健在だ。
戦争や差別に反対すること、世界中の民謡を歌うこと、とがったジョークで人を笑わせること、これらが渾然一体と混ざり合う。
まさに、フォークルは「芸能」というものの本来あるべき姿を体現しているかのようだ。
何しろ、レコードの歌詞カードの細か〜いところまでオモシロイ!!
フォークルのラジオ人気の話に戻ろう。
面白いことに、京都では「イムジン河」がヒットし、神戸では「帰ってきたヨッパライ」がヒットした。
フォーク・クルセイダーズのところに、レコード会社の連中がやってきてプロデビューの話を持ちかける。
意外にも、このとき反対したのは加藤和彦で、北山修は加藤を説得したという。悩んだ末に出した答えは、「じゃあ1年だけなら」。
平沼義男はプロにはならず、もうひとりメンバーを入れることに。
北山修は、杉田二郎を推薦。加藤和彦は、端田宜彦を推薦。
結果、フォークルは、端田宜彦が加入することで、プロデビュー。
名前も「フォーク・クルセイダーズ」から、「ザ・フォーク・クルセダーズ」にちょっとだけ改名。
フォークルの登場が日本におけるフォークソングの幕開けとするなら、その始まりが「イムジン河」と「帰ってきたヨッパライ」という2つの歌なのは、とても面白い。
ひとつは、韓国と北朝鮮の平和を願う歌。もうひとつは、ナンセンスなコミックソング。
フォークソングは、「朝鮮半島」と「お笑い」で始まったのだ。これは、「世界平和」と「芸能」とも言い換えられる。
ぼくは、このことをなんとなく誇りに思いたい。
ほかの音楽シーンにも触れたい。
1965年に開催された「第1回フォークソング・フェスティバル」で歌手としての活動をスタートさせた伊東きよ子は、翌66年に渡米、ニュー・クリスティー・ミンストレルズの正式メンバーとなる。なんたるアクティブさ!
ビザが切れて、この1967年に日本に帰って来た伊東は、今度は渡辺プロと契約、コロムビアレコードより「花と小父さん」でデビュー。
これは浜口庫之助の作詞。マイク眞木の「バラが咲いた」も彼の作品である。「フォーク」という音楽は、流行りものの音楽ジャンルのひとつとしか捉えられていなかった。だから、歌謡曲とフォークソングの融合が存在した。
日本という国は、島国ゆえか、そうやって外から来た文化を何でも取り入れ、また日本風にし、さらには無関係のもの同士を混ぜ合わせ、新しいものをつくってきた。それが、日本文化の面白さだ。
しかし、「フォーク」も「ロック」も、そこには単なる音楽ジャンルのひとつずつではなく、哲学やコンセプトのようなものがあったはず。頭のいい人たちには当然そんなことはお見通しだったろうが、しかしヒット曲をつくる際には、そんなものは邪魔なだけだ。
「この広い野原いっぱい」や「今日の日はさようなら」がヒットした森山良子は、ジョーン・バエズの来日コンサートで、急遽、舞台にあげられてしまい、困惑するばかりだったという。突然のように、憧れの存在と並べられ、「日本のジョーン・バエズ」なんて世間から呼ばれてしまったら、かしこまってしまっても無理はない。
日本人は、すぐに「和製ジョーン・バエズ」だとか「和製ボブ・ディラン」、或いは「和製ビートルズ」などと言いたがる。それは、外の文化を取り入れ取り入れ進化していった日本という国のいわば恥ずかしい性格だ。それは面白いことでもあるが、言われた方はたまったものじゃない。だって、アーティストはオリジナルを目指すものなのだから。
そうしてカレッジ・フォークや歌謡フォークが大通りに流れるとき、たとえば高石友也の「想い出の赤いヤッケ」や中川五郎の「主婦のブルース」が、誰か新しい世界を模索している若者の部屋に流れていたかもしれない。
石原裕次郎が「夜霧よ今夜もありがとう」と歌うとき、三波春夫が「世界の国からこんにちは」と唸るとき、その霧の向こうに、その世界の裏側に、高石、中川、岡林、フォークル・・・といった面々がいた。
10月3日、クイーンズのクリードムーア精神病院にて、ウディ・ガスリー、永眠。
アメリカン・フォークの祖を苦しめたハンチントン病は、いまだ治療法が確立されていない。
ウディよ永遠なれ!!
彼から、すべてが始まった。
あの大恐慌時代、ダストストーム吹き荒れる、悲しいアメリカの大地。
さすらいの歌うたい、そして根っからの左翼労働者、ウディ・ガスリーはいた!
ピート・シーガーは、環境保護団体などの市民運動に深くコミットしながら、歌いつづけていた。
またボブ・ディランは、ナッシュビルで録音した「ジョン・ウェズリー・ハーディング」をリリース。
世界は終わらない。地球は回り続ける。
夢はつづく!!

Bob Dylan / John Wesley Harding
ビートルズは、ライブ・ツアーからスタジオでのレコーディングに活動をシフトし、8枚目のオリジナルアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」は実験的なサウンドに溢れ、世界初のコンセプトアルバムと呼ばれるようになった。
ジャケットには、メンバー4人とともに多くの著名人が載っており、その中にはボブ・ディランの姿も見られる。来日のときにジョン・レノンが買った福助人形も・・・!?
ローリング・ストーンズはというと、麻薬容疑でミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ブライアン・ジョーンズの3人が逮捕。
アルバム「サタニック・マジェスティーズ」は、ブルーズをはじめとする黒人音楽を主体とするストーンズ本来の姿とはかけ離れ、メンバーからも不評だった。
ビートルズ、ストーンズともに、サイケデリックな世界に迷い込んだ1967年、アメリカ大陸はというと、バッファロー・スプリングフィールドのブルース・パーマーも麻薬でツアー中にカナダへ強制送還。しかし、復帰後になんとかセカンドアルバム「バッファロー・スプリングフィールド・アゲイン」をリリース。
こうして見ると、いつの時代だって、音楽好きな若者が麻薬のひとつもやってみたくなるのは、しょうがないんじゃないか!?と思ってしまう。だって、ロックスターたちがやってるんだから、ちょっと試してみたいのもしかたない。
ぼくたちの住むこの世界中が、勝新太郎のパンツなのかもしれない。
そう考えると、フォークと呼ばれる音楽の旗手たちは、ボブ・ディランと南正人を除いて、麻薬とほとんど無関係である。

The Beatles / Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Tje Rolling Stones / Their Satanic Majesties Request

Buffalo Springfield / Buffalo Springfield Again
あんまり欧米のロック・シーンまでをもカヴァーしようとすると、文章が長くなり過ぎになってしまうのだけど・・・。
でもいろいろな人のことを書いて無関係に見える存在同士を結びつけていく面白さを提示したい・・・!
特に、やっぱり1960年代後半から70年代前半というのは、日本もアメリカもイギリスも、音楽のみならず様々なアートがアンダーグラウンドから新しい動きを生んでいた時間のようだ。だから、書き残したいと思う連中がぞろぞろいて、まったく困りものである。
なので、あとちょっとだけ。
多彩な芸術活動を展開していたアンディ・ウォーホルに認められた、ルー・リード率いるバンド、ヴェルベット・アンダーグラウンド。
ウォーホルは、女優でモデルのニコをボーカルにして、バンドをレコード・デビューさせる。
ルー・リードたちとプロデューサーであるウォーホルとの関係およびニコの参加は、このファースト・アルバムのみで終わり、商業的にも成功しなかった。
あっ、このバナナのジャケット・・・ロックに疎いフォーク・ファンでも、見覚えがあるはず・・・!

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド / ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ
ホテルで高田渡の前にあらわれたのは、ピート・シーガーだった。
3年前に書いた拙い英語の手紙、「そっちに行って音楽の勉強をしたい」というまっすぐなピートへの手紙。
ちゃんとアメリカから返事をくれた。「それなら英語を勉強してからおいで」。
でも結局、アメリカには行かなかった。
日本で、東京で、フォークの仲間とも出会った。
明治大正の演歌師、添田唖蝉坊や添田さつき、或いは沖縄の現代詩人、山之口貘。いつのまにか渡のポケットの中には、アメリカン・フォークのほかにも宝物がいっぱい詰まっていたから。
「やあ、君だったのか! 手紙をくれたのは!」
ピート・シーガーは、遠い日本から送られてきた手紙をちゃんと憶えていて、翌日の日比谷公会堂でのコンサートの招待券まで渡にくれた。
コンサートが終わると、音楽評論家たちと観客たちで、ピート・シーガーについての座談会が始まった。
当時は、歌と討論がセットでフォーク・コンサートというものが多かったようだ。それほど、歌とは何なのかを真剣に考えていた時代だったのだ。
そこには、PPMフォロワーズの小室等もいた。
高田渡が手を挙げて、言う。
「外国の曲をそっくりそのまま歌うんじゃないんだ、ということを教えてくれた気がします。ぼく自身、日本語としての歌を歌わなきゃいけないと思うし、いまそういう実験をしています」
少し、場がキョトンとなった。
「いまそういう実験をしています」
高田渡は、確かにそう言ったのだ。
きょうのエンディングテーマは、ザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」と「イムジン河」。
「帰って来たヨッパライ」は、あえて!2007年にテレビ番組で、加藤和彦と坂崎幸之助がボサノバ・バージョンで歌ったもの。神様役は、泉谷しげる!