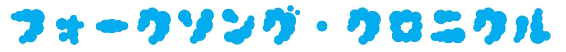■1967年(昭和42年)
ババンババンバンバン・・・
ババンババンバンバン・・・
タイムマシン「フォーキー」の機内は、四畳半である。
そこはコクピット兼居間であり、せんべい布団が敷かれている。
少年ワタルと三毛猫ピックは、1年未来に行くごとに、研究の疲れを癒すために最低8時間は睡眠をとることにしている。
いよいよ、日本におけるフォークの幕開けといえる、ザ・フォーク・クルセダーズの自主製作盤「ハレンチ」が発売される1967年。
目を覚ましたワタルとピックは、これまでのアメリカにおける1930年頃から1965年頃までのフォークソングの歴史と、そして日本における1960年代のモダンフォークブーム、GSブーム、3人のシンガーソングライターのことと、ノートを見ながら復習した。
さあ、いよいよもって、フォークルやURCや中津川フォークジャンボリーだ。
そしてワタルのご先祖様であると思われている高田渡もギターを持って世界に登場する。
しかし、外からは、妙に愉快な歌が聴こえてくる。
フォーク・クルセダーズも随分とコミカルなことをしたグループとは知ってはいるが、どうも様子がおかしい。
外に出てみると、昭和元禄。
ゴジラとガメラとギャオス、それからグズラまで空を飛び交っている。
東京タワーにはキングコングがよじのぼり、喫茶店では仮面の忍者赤影が「天才バカボン」と「あしたのジョー」連載の少年マガジンを読んでいる。
駄菓子屋でチョコボールを買ったワタルは、それをポリポリ食べながら、電気店の前までやってきた。
ババンババンバンバン・・・
ババンババンバンバン・・・
さっきから聴こえてくる音の主は、この電気店のテレビだ。
手拭い頭に巻いた変なおじさんたちが真面目な顔して、しかし滑稽な踊りを踊りながら、声を揃えて歌っている。
クレージーキャッツの弟分的存在のザ・ドリフターズだ。
といっても、ザ・ドリフターズというコミックバンドは歴史が古く、様々なメンバーの入れ替えが行われてきた。古くは、坂本九だってドリフにいたことがある。
このときのドリフは、いかりや長介、仲本工事、高木ブー、加藤茶、荒井注。
まだ志村けんは付き人にもなっていない。
「冗談音楽」という笑いのジャンルは、テレビの成長とともに流行しなくなっていった。クレージーキャッツをはじめとするコミックバンドは、楽器を使った大掛かりな笑いが素晴らしいのだが、クレージーはそれが植木等だけの歌唱にスライドしていき、ドリフはコントにスライドしていったといえる。
そしてドリフの持ち歌は、クレージーおよび植木等の無責任シリーズの歌とは違い、お子様からお年寄りまで楽しめるような、どこか牧歌的な感じだ。
クレージーキャッツはオトナの笑いだった。
ドリフターズはお茶の間の笑いだった。
芸能で何より大切な基本は、笑いである。
クレージーキャッツやドリフターズ、ピート・シーガーやビートルズ、そのいずれもがいたからこそ、フォーク・クルセダーズも生まれたのだと私は思う。
電気店のショーケースにワタルとピックが、覗き込む。
「いい湯だな」は、ドリフのオリジナル曲ではない。いわば民謡、これもまたフォークソングだ。
だけど、これに「ビバノン・ロック」なんというサブタイトルをつけてしまうのだから、たまらない。
これからロックの言葉のもとに切磋琢磨するミュージシャンたちからしたら・・・!
そうだ、フォークもロックも、「いい湯だな」にすべて詰まってる!!
・・・言い過ぎました。
・・・と、少年ワタルが研究を纏めたところで、どうやら、この陽気な歌とともに、60年代ポップス編は幕を閉じるようである。
次回は、もう一度、1967年。今度こそフォークルの登場だ。
・・・って、だいたい、「ビバノン」って何なのよ!?
ババンババンバンバン・・・
ババンババンバンバン・・・