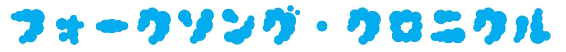■1965年(昭和40年)
ここからは1年ずつやっていこうと思う。
ニューポート・フォーク・フェスティバルで、ボブ・ディランの鳴らしたエレキギターの音が響いたとき。
京都で、ひとつの出会いがあった。
雑誌「MEN'S CLUB」の投稿欄で「フォーク・コーラスをつくろう」と呼びかけた加藤和彦のところに、自転車に乗って北山修がやって来たのだ。
さあ、いよいよフォーク・シーンの幕開けだ。
第1次ザ・フォーク・クルセダーズは結成された。
メンバーは、加藤和彦、北山修、平沼義男、井村幹生、芦田雅喜。
一方、遠く離れてカナダのオンタリオ。
スティーヴン・スティルスとリッチー・フューレイが、ニール・ヤングに出会っている。
「フォークソング・クロニクル」は、おもに、自分の言葉で歌う新しい音楽としてのフォークソングと、そして日本語によるロックンロールの物語である。
こちらの出会いも、日本語ロックの代表格のバンドに関係してくる。
日本に戻ろう。
ザ・スパイダースは、この年、「フリフリ」でレコードデビュー。
この曲は、かまやつひろしの作詞作曲。
クレージーキャッツはというと、めでたいことに結成10周年。
あいかわらず映画や舞台に大忙しだった。

ザ・スパイダース / ザ・スパイダース:コンプリート・シングルズ
さて、ザ・フォーク・クルセダースが結成されたのはいいものの、まだ表舞台に大きく登場するには少し時間があるようだ。
60年代後半からのフォーク黎明期の歴史が始まる前に、3人のシンガーソングライターを紹介したい。
そのうちの1人のお話。
丸山明宏(現・美輪明宏)がかねてより歌っていた「ヨイトマケの唄」がレコードになった。
同性愛者であることのカミングアウトと、従来のシャンソンのイメージと違うキャラクター像から、丸山明宏は人気を失っていた。
丸山は、そんな中で、自分で歌をつくるようになっていった。
「ヨイトマケの唄」は、炭坑町でコンサートを行ったことをきっかけにつくった歌。
建築現場などで働く労働者のことを、ヨイトマケと言った。重い滑車や綱などを持ち上げたり引き上げるときの掛け声が、言葉の由来だ。
いつも煌びやかな衣装を纏っているシャンソン歌手が、労働者の歌を歌う。貧しい者の歌を歌う。
そんなことは初めてのことだっただろう。
テレビのワイドショーで紹介されて、歌は多くの人の胸を打ち、丸山明宏も人気を取り戻した。
ブラウン管の向こうに、男の姿で歌ってみせる丸山明宏の姿があった。
長崎から東京へやって来て、ホームレス生活をした彼女にもまた、一家離散しアメリカをさすらったウディ・ガスリーと通じるものがある。
どんなきれいな唄よりも どんなきれいな声よりも
ぼくを励ましなぐさめた 母ちゃんの歌こそ世界一
炭坑もまた、歴史の歯車の中で大きく動き、そこには民衆たちの苦しみと、そこから生まれる本物の歌が存在した。
労働争議、炭塵事故、ガス事故・・・。
しかし、石炭から石油へとエネルギーは世界規模でシフトチェンジし、その記憶も薄れていっている。
「三池の子守唄」などの炭坑節、そこに生きた人々の歴史もまた、民衆の歌、すなわちフォークソングである。
もうひとつ違う話題を。
この年、3人の男娼に性転換手術(性別再適合手術)を行った医師が逮捕さた。いわゆるブルーボーイ事件である。
医師は麻薬を吸っていたことでも逮捕されたが、手術を行ったことのほうが重い罪とされた。
このことがきっかけで、日本の性同一性障害者は、闇で手術をするか、海外で手術をするかの2択を選んできた。
ガイドラインなどがつくられ法的に手術が認められた現在も専門医があまりに少ない理由に、この事件の影響がある。
しかし、ボブ・ディランの歌うように、時代は少しずつ変ってゆく。
いつまでも、時代は変わり続けてゆく。
価値観や考え方、そして正義や常識も、変わり続けてゆく。
この世界に、私たち人間が生きているかぎり・・・。
アメリカの青い空に、ピストルの音が響いた。
マルコムXが射殺された。
西暦1965年。
60年代も、半ばを過ぎた。
昭和30年代ってやつの終焉。
きょうのエンディングテーマ、「ヨイトマケの唄」。
のちのフォークシンガーたちにも影響を与えているしるしとして、泉谷しげるバージョンを。
おやすみなさい。