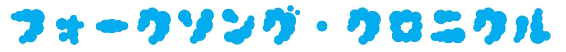■1961年 / 昭和36年
ロカビリーブームはとうに終わり、クレージーキャッツはまだまだ大人気。
ほんとうは日劇ウェスタンカーニバルなどにおけるロカビリーブームについても研究したいところだが、なかなかこのままでは高田渡も岡林信康もずっと出てこないんじゃないかというほどにクドクドとやっているので・・・。
なので1950年代にまでまた遡ると、なんだかニューポート・フォーク・フェスティバルでエレキを鳴らして野次を受けてるままじゃ、ボブ・ディランがかわいそうだ。
ほんとうなら、ここで1965年と題して、ザ・フォーク・クルセダーズが登場するところだったのだが、どうしても「スーダラ節」というタイトルの回をつくりたくて・・・!
なに、コミックソングや喜劇のエッセンセンスは、フォークやロックにも繋がるものだ。(60~70年代に登場したフォークやロックのミュージシャンたちは、喋りが面白い人が多い)
音楽という芸能を語っている以上、クレージーキャッツを素通りするわけにはいかない。
ときはナベプロ全盛期。
60年代どの年に行っても、クレージーキャッツは存在する。
正式名称は、ハナ肇とクレージーキャッツ。
歌と同時に、テレビ、そして植木等主演の映画「無責任男シリーズ」。
この60年代に青島幸男らが描いてみせたサラリーマン像が、当時の高度経済成長のニッポンを支えるお父さんがたを勇気づけたか、それともムカッとしたか・・・とにかく、クレージーキャッツはそこにいた。
満員電車に揺られる月給取りの疲れを吹き飛ばすかのように、さまざまなお気楽な台詞、気の抜ける文句が踊る。
いまでは考えられないだろう。
この時代では、芸能は芸能だった。物語は物語だった。
観客たちは観客だった。視聴者であり、大衆であり、ファンだった。それ以外の何者でもなかった。
「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ~」と植木等が歌うとき、決して、「なんだ、芸能人の植木等なんか、サラリーマンの苦労も知らないくせに!」なんというブーイングはあり得ない。
いまだったら・・・ダメだ、日本人の芸能芸術に対する考えが違う。
21世紀は、誰もが発信者であり受信者であり、すべては共有される世界である。
そこに、たとえばクレージーキャッツがお気楽にド~ンと登場し、無責任にホラを吹いてみせたところで、それは一瞬でまたたくまに消化されてしまうだけかもしれない。
だけど、この混迷の時代にほんとうに必要なものは、「人生で大事なことはタイミングにC調に無責任」と歌ってみせる、クレージーキャッツ・スピリッツだと思うのだ。
人間なんて、そんな大したもんじゃないだろう、と教えてくれる。
どうせ生まれてきたんだからパーッといこう!と、あきらめて笑っちゃう。
とめどない理屈と終わりのない欲望のこの時代に、何より大切な処方箋だと思う。
ところが、いまの時代ときたら・・・「無責任」どころか「自己責任」ときたもんだ。
まことに遺憾に存じます~!

ハナ肇とクレージーキャッツ / 50周年記念ベスト 日本一の無責任大作戦
また、この年には、ザ・スパイダースも結成している。
まだ初期のメンバーで、7人全員が揃ってはおらず、メンバーチェンジを繰り返した。
同じ頃にイギリスでのろしを上げたビートルズに触発され、マージー・ビートの音を模索していく。
かまやつひろし(現・ムッシュかまやつ)は、それまで、日劇ウエスタンカーニバルに出演していた。
ロカビリー三人男には数えられなかったものの、その音楽性、そして映画出演と活躍し、彼を「日本で最初のロックミュージシャン」と呼ぶ声も多い。
懐の広い不思議な人物、かまやつひろし。
彼もまた、のちに、フォークシンガーたちに関わっていくことになる。
■1962年 / 昭和37年
FENからピーター・ポール&マリーの歌が聴こえてきた。
青年は、何かを見つけた気がした。
彼の名は、小室等。
すべてのフォーク・シーンを見届ける男。
時計の針が動き始めた。
アメリカでは年の暮れに、ボブ・ディランがレコードデビュー。
海の向こうから見た「フォークソング・クロニクル」と、こちらから見た「フォークソング・クロニクル」が、重なっていく・・・!

Peter, Paul and Mary / Peter, Paul and Mary
■1963年 / 昭和38年
ボブ・ディランが時の人となりつつあり、ミシシッピ・ジョン・ハートが「再発見」された1963年。
日本に、カレッジ・フォーク、キャンパス・フォークの風が吹き始めた。
マイク眞木は、モダン・フォーク・カルテットを結成。アメリカの本家と同じ名前だ。
カレッジ・フォークは、アメリカのPPMやキングストン・トリオ、ブロードサイド・フォー、モダン・フォーク・カルテットといったアメリカのフォークグループに感銘を受けた若者たちによる音楽だった。
それらは、なんというか、きちんとしているのだ。
もっとも、PPMやキングストン・トリオ、モダン・フォーク・カルテットが、ピート・シーガーらの模倣なのであるから、それも当然のことになる。
ウディ・ガスリーの「わが祖国」で、歌詞の最後のほうの部分があまり歌われないのと同じで、毒を抑えた小ぎれいな風景が大衆は好きだ。
もちろん、きれいなのも、おとなしいのも素敵だ。
だけど、ほんとうに大切なことは、いつだって、真ん中にある。
ぼくらは、それをしばしば見ないふりをする。
アメリカでは、ワシントン大行進だ。
若者よ、キャンパスを飛び出せ! 過去現在未来を通じてだ! 小ぎれいなばっかりじゃ、だめなときもある。
でも、これは確かに、歌というもののあり方のひとつだ。
ヨーロッパ移民の民謡と黒人たちの霊歌がアメリカのフォークソングとなり、ウディ・ガスリーやミシシッピ・ジョン・ハートやレッドベリーがそれを歌い、そしてピート・シーガーも歌い、PPMがまた歌う。
そうして、たくさんの人に歌が伝わる。フォークソングが、歌というものの本来のカタチを教えてくれる。
だから、カバーじゃなくて、誰が歌ってもいいし、詞や曲をどう変えてもいいし、それぞれがそれぞれの歌で、そしてひとつの歌なんだと思う。

The Kingston Trio / Leaders of The '60s Folk Revolution

Modren Folk Quartett / MFQ LIVE Archive Series
一方、演劇の世界では、唐十郎が「シチュエーションの会」を旗揚げ、のちに「状況劇場」と名を改める。
歌舞伎などの旧劇へのアンチテーゼが新劇だった。
そして今度は、新劇へのアンチテーゼとして、アングラ演劇が誕生していく。
「アングラ」という言葉はあまり使いたくはないけど、このアングラ演劇と、あともう少ししたら登場するアングラフォーク、関西フォークとは、一部で密接な関係を築くので、演劇のことも併せて書いていきたい。
唐十郎の登場は、70年代に東京・新宿を中心に巻き起こるアングラ文化、その前触れである。
テレビでは「キューピー3分間クッキング」の放送が始まり、お父さんがたにはサントリービールの栓がシュポッと抜かれた。
この年のヒットは、坂本九の「明日があるさ」。
おっと、さっきのクレージーに続いて、またまた作詞が青島幸男だ。
曲は、もちろん中村八大。
ああ、坂本九、いまの時代、こんなに、こんなに、めいっぱい笑って歌うシンガーがいるだろうか?
こんなにも、ただ目の前にいる人に元気をあげようとする純真な芸能。
感動せしは、歌謡曲の素晴らしさ。

坂本九 / CD&DVD THE BEST ~上を向いて歩こう
■1964年 / 昭和39年
東京オリンピック。
もはや戦後は終わったかのような顔をして、日本は高度経済成長の坂道を上がっていき、そして公害という足跡をつくっていった。
「誰か一部の人間が儲かってるだけじゃ」と、目玉の親父は墓場鬼太郎に教えるだろう。
水木しげるは、この年、月刊漫画「ガロ」にデビュー。
さて、音楽の話。
マイク眞木に続いて、黒澤久雄もザ・ブロードサイド・スリーを結成。
翌1966年にはメンバーが増えて、ザ・ブロードサイド・フォーに。
小室等も、その名もずばり、PPMフォロワーズを結成。
カレッジ・フォークの面々は、のちのアングラな連中と比べて、あまりにきらびやかだ。サッパリしている。
こうした60年代前半のカレッジ・フォークの存在が、60年代後半のアングラフォークの登場を映えさせる・・・!
お子様たちには、新発売の「かっぱえびせん」をどうぞ。
ちょっとおませな学生さんには、「平凡パンチ」創刊号。
ディランがイギリスに行ったように、ビートルズもアメリカへやってきた。
フォークとロック、アメリカとイギリス、伝統と革命、さまざまなものが混じりあい、世界は一瞬ごとに生まれ変わっていく。
きょうのエンディングテーマは、植木等メドレーと、それから坂本九の「明日があるさ」。
フォークソング襲来の前に、絢爛でナンセンスな歌謡曲の世界を存分に感じよう!!
金のない奴ぁ俺んとこへ来い! 俺もないけど心配すんな!
そのうちなんとか・・・なるだろう~♪
上を向いて歩こう! 明日があるさ・・・!