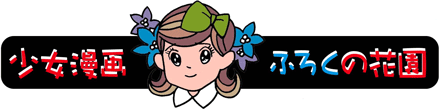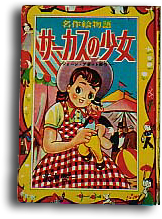| 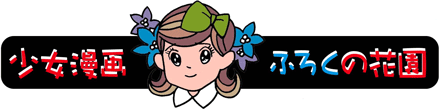

昭和30年代の少女雑誌ふろくの特徴として、まず別冊ふろくが目立っていたことがあげられます。
例として、ある月の『なかよし』『りぼん』のふろくを見てみましょうか。
| 『なかよし』昭和31年4月号のふろく
・別冊 名作絵物語[家なき子]
・別冊 少女絵物語[みかえりの塔]
・別冊 けっさくまんが[ぽっくり物語]
・別冊 名作絵物語[子じか物語]
・別冊 少女歌物語[荒城の月]
|
|
| 『りぼん』昭和32年12月号のふろく
・別冊まんが りぼん文庫
[妹マギー、アニーよ銃をとれ、五つ木のこもりうた]
・別冊まんが[めぐみちゃん]
・別冊 クリスマスブック
・別冊[ルパン集]
・クリスマス・セット[抒情画、カード、デコレーションのセット] |
|
このように毎月必ず複数の別冊ふろくがついていました。もちろんそればかりというわけではないのですが、小物中心で年に数回ほどしか別冊ふろくにはお目にかからない、という現在の状況とはかなり違います。
この傾向は少女雑誌に限らず当時の少年雑誌ふろくにも見受けられたのですが、その背景には運輸省によるふろくの材質規制があったようです。昭和29年5月のこと、各誌間で繰り広げられていた、ふろくの豪華さを競い合ういわゆる「ふろく合戦」がエスカレートし、これに音をあげた運輸省はふろくに使用できる材質について制限をかけます。これにより材木や金属、ガラス、布などを用いたふろくは雑誌なみの運賃では扱えなくなりました。こうして、本をはじめとする紙製品がふろくの中心になるという事態を招いたのです。
当時の別冊漫画は現在のものと同じように、100ページ強という少し厚めの本に3作品ぐらいがまとめられているものが多かったのですが、中にはハードカバーで市販の単行本と同じくらいきちんとした作りになっていたものもありました。内容も「小公女」「フランダースの犬」といった世界の名作をとりあげたりと格調の高さを感じさせます。「マンガは低俗だ」と考えている親にも子どものために雑誌を買ってあげてほしい、という作り手側の願いがあったのかもしれませんね。
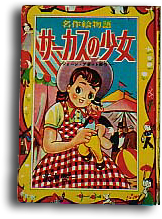
また昭和30年代半ばごろからは、連載漫画の続きを別冊ふろくで楽しむという新しい試みも始まりました。1作品で1タイトル、これが毎月2〜3冊つきました。こんなにたくさん本がついたらブ厚くなって本誌に挟むのに困るのでは、と思われるかもしれません。しかし創刊当初はともかくとして、このころになると1冊のページ数はほとんどが30前後と少なく、薄くなってきています。
この傾向は昭和40年代はじめまで続き、漫画の内容だけでなく様々な版形とカラフルな色使いで、外見でも少女たちの目をひきました。
国会図書館で当時の『なかよし』を調べていたときに、ひとつ気に入った連載漫画があって読んでいたのですが、ふろくがなかったために続きがわからず悲しい思いをしました。最終回もふろくだったため、どのように完結したかも結局わかりません。本誌とふろくでワンセット、これはなかなか読者泣かせでもあるのです。
なかなか女の子らしい内容になりませんが、次回も地味目のテーマにおつきあいくださいませ。
2003年7月30日更新
ご意見・ご感想は webmaster@maboroshi-ch.com
まで
2.『りぼん』『なかよし』が生まれた時代
1.ふろくって何?
→ |