
|
トランポリン・松岡
第七回『嵌った嵌った、森繁の社長シリーズとアレコレ』
|
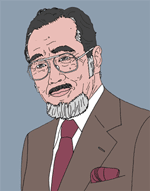
|
MACに少し疲れ、棚に押し込んでいるビデオテープを整理していたら、TVで放送され映画を録画したのだろう「森繁久彌と社長シリーズ」と背書きされたテープが出てきた。やった、ラッキーと言う感じで嬉しく懐かしく再生したが、少し赤っぽい映像で車が舗装されていない道路を走る出だしのシーンを見た瞬間、森繁の社長シリーズとしては役者が揃っていないと言うか少しがっかりした作品であることを思い出しテープを止めた。
僕は二十歳後半から十年程、突然かかった流行り病のように森繁映画とレコードに凝ったことがある。
 ただ、昭和四十年前後の一番油が乗った森繁好調期のことではない。東宝の看板映画・森繁の社長シリーズも低迷、シリーズが制作されなくなっていた頃で、それこそ十年程遅れて森繁映画をみて燃えた僕なのである。 ただ、昭和四十年前後の一番油が乗った森繁好調期のことではない。東宝の看板映画・森繁の社長シリーズも低迷、シリーズが制作されなくなっていた頃で、それこそ十年程遅れて森繁映画をみて燃えた僕なのである。
本来、森繁の社長シリーズはサラリーマンの悲哀や笑いを描いた大人の映画。シリーズがヒットしている時期に中学生の僕が森繁を好んでみていないのは当然で、ずっと後にグーンと遅れて、ある日突然、森繁映画に全身ドップリ嵌りこんでしまったわけで、最近よく言われる僕のマイブームなのである。
それこそ始まりはTVの深夜放送でみた社長シリーズ。それで、コリャ面白いーッとなったのであるが時すでに遅く、森繁レコードの廃盤と同じで森繁映画は過去のモノとなっていて、顔を床にこすりつけて頼んでも無いモノは無いと言われる感じに時代の流れは甘くなかった。
それならばと、浅草の三本五百円のオールナイト営業映画館などの森繁映画上映情報を見つけては通い始めた僕ではあるが、それが、藁をつかんで最後の足掻き?と言うか日本映画の名作がけっこうあって、当然、社長シリーズ以外の森繁出演映画もみるチャンスに恵まれ、僕の心は、飛び乗った瞬間に扉が閉まった終電感覚のホクホク状態。
そんな一本、僕の心の名作は、一九五五年(東宝)久松静児監督の「渡り鳥いつ帰る」。森繁は、酔って川に落ちて事故死した自分とは関係ない本当に自殺した女と入水心中したように周囲に誤解させたまま死ぬ男を演じるのであるが、陽はまた昇る的人生の真実と言うか、彼が死んでも世の中の生活は全然変わらずそのまま続いて行くという無常感に、若い僕は涙がボロボロ。遺体の裸足の裏をカメラがなめるあのシーンを僕は一生忘れられない。
勿論、穏やかなモノでは、森繁が村の中年警察官を演じあの二木てるみが子供を演じる一九五五年(日活)久松静児監督の「警察日記」も悪くはないが、古い白黒日本映画によくある日常の中のちょっとした出来事に親子の情が描かれそのまま大きな山もなく終わる感じが僕の中では今一つで、大好きにはなれない作品なのだ。
そこで、森繁と言えば、やっぱり一九五六年〜一九七0年頃まで共に二十数本続いた喜劇駅前シリーズやあの社長シリーズとなる。アドリブなのかさりげなく演じる彼の相手を弄り突く感覚・絡む演技は絶妙で物凄く面白く、シリーズをみる度に魅せられ思い出す度に僕などグフッと笑いが出てしまう。
 淡路千景や加藤大介、若さムンムンと黒沢年男や桃屋のごはんですよのCMなんかをしていた鼻のデカい三木のり平、森繁社長に引きづり回される素人クサイ若い真面目社員小林桂樹も出てくる社長シリーズは素晴らしく、必ず「パッと行きましょう、パッと」と言いながらいい加減なことばかり言う三木のり平に乗せられて宴会芸の乗りでハレホレ踊るシーンなど何度みても大爆笑。シリーズを通じて森繁は歌や踊りを次から次に披露、もう森繁の一人舞台。かくし芸大会的な所もあって僕などウハウハワクワクであった。 淡路千景や加藤大介、若さムンムンと黒沢年男や桃屋のごはんですよのCMなんかをしていた鼻のデカい三木のり平、森繁社長に引きづり回される素人クサイ若い真面目社員小林桂樹も出てくる社長シリーズは素晴らしく、必ず「パッと行きましょう、パッと」と言いながらいい加減なことばかり言う三木のり平に乗せられて宴会芸の乗りでハレホレ踊るシーンなど何度みても大爆笑。シリーズを通じて森繁は歌や踊りを次から次に披露、もう森繁の一人舞台。かくし芸大会的な所もあって僕などウハウハワクワクであった。
実は、森繁映画を語るにはこれが一番という忘れられないシーンがある。旅館から温泉、怪談に競馬等二十本以上ある喜劇駅前シリーズの中のどれかは思い出せないが、確か、喜劇駅前シリーズ中の一本で、フランキー堺を相手にブラジル帰りか二世を森繁が演じるのだが、赤いアロハか何か派手な服装は雰囲気があってコレがまた森繁によく似合っていた。
それが、喫茶店で、女性を口説くような感じでフランキー堺の手を取って離さず、話しながらギュッと握りしめたり優しく撫でたりの連続。その森繁の弄りを受けて立つフランキー堺もコレ滅茶苦茶ウマイーッ。
ついには掌に指で文字を書いたりと散々弄り回すのだが、話を聞きながらも全身を痙攣気味に身震いさせながら体をクネクネ揺すり、時々身を反らして「アウッ」と喘ぐように息を漏らし嫌がりながらも目を閉じウットリする表情を見せるフランキー堺に、最後は、一方的にアリガータアリガータなどとスペイン語か何か言って、森繁は大袈裟に喜ぶのだ。

その「アウッ」の表情やクネクネシーンの変な男二人の絡みの可笑しさを誰も激しくは笑わず(とどめは、フランキー堺に耳打ち話をするフリをして森繁がその耳にフッと息をかけていた、ような気もするが)、僕は一人大笑いも何だか何なので、映画館で腸捻転を起こしそうなくらい我慢。大笑いを必死にこらえた。
現在でも雑誌等でそんな駅前や社長シリーズの記事を偶然見ることがあるのだが、昭和四十年前後と言えば中学生。僕はまだ森繁映画も面白さを知らず、同じ東宝の特撮映画である海底軍艦やマタンゴといった辺の空想冒険・怪奇映画を父に誘われみていたような時期で、後年、実に勿体無いことをしたと超大後悔をした僕なのである。
後の後悔先に立たずを実感。出遅れた分を取り戻す感じで過去を遡るように森繁映画に目を光らせ、偶然見つけて買った「森繁久彌愛唱歌集」の歌声にも魅せられた僕は、銀座や新宿等のレコード店回りをして廃盤直前のレコードを買い求め、ストーカーではないが賃貸契約切れを期に森繁が住む小田急の千歳船橋に引っ越した。
当時、仕事で文化放送ラジオの小冊子にエッセイを書いていたことがあるのだが、ペンネームを森屋繁一にしていた程、僕は嵌っていたのだ。
帝国劇場であの屋根の上のバイオリン弾きが上演された時も五千円のチケットを購入。途中の休憩時間にはバナナやお菓子を頬張るオバサン軍団の間に座ってみた僕であるが、やがて、森繁はあの懐かしく面白い駅前や社長シリーズからどんどん離れてゆき、僕には可笑しくも面白くもない大俳優に変身。
森繁は僕の視界から消えた、と言うより僕の方で熱が冷めてもう森繁を追い捜さなくなったのである。
この十年、僕は、作品が岩のように力強く穏やかな昭和十年〜三十年の梅原龍三郎に夢中で信州まで出かけたり、一年に一度は尾道白樺美術館に通っている。現在の僕と年齢が近い五十三歳・昭和四十一年にアトリエで撮られた写真は額にいれMACの横に置いてあり、72B/1972年生まれ、僕と旅してきた十四インチの赤いナショナル白黒TVの脇には、彼の昭和十年・桜島(赤)の複製が並んでいる。
詩人北原白秋に憧れ、森繁映画に魅せられ、画家梅原龍三郎に嵌っている僕は、彼らと時代の中で微妙にすれ違い、地方駅の列車ホームでポツンと一人冬空を見上げるような感触を覚えながら歳ばかりとってゆく。
窓の向こう側の空は青く、懐かしいロス・パンチョスのメ・ボイ・パル・プエブロを聴きながら、僕はMACのリターンキーを軽く弾いた。

2002年10月1日更新
第六回『ジュンとネネではなく、VANとJUNの話』
第五回『夏は怪談映画、あの映画看板も僕を呼んでいた。』
第四回『青春マスターベーション』
第三回『ワッチャンの超極太チンポ事件』
第二回『中高年男性、伝説のモッコリ。スーパージャイアンツ』
第一回『トランポリンな僕のこと、少し話しましょうか。』
→
|


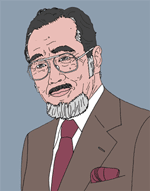
 ただ、昭和四十年前後の一番油が乗った森繁好調期のことではない。東宝の看板映画・森繁の社長シリーズも低迷、シリーズが制作されなくなっていた頃で、それこそ十年程遅れて森繁映画をみて燃えた僕なのである。
ただ、昭和四十年前後の一番油が乗った森繁好調期のことではない。東宝の看板映画・森繁の社長シリーズも低迷、シリーズが制作されなくなっていた頃で、それこそ十年程遅れて森繁映画をみて燃えた僕なのである。 淡路千景や加藤大介、若さムンムンと黒沢年男や桃屋のごはんですよのCMなんかをしていた鼻のデカい三木のり平、森繁社長に引きづり回される素人クサイ若い真面目社員小林桂樹も出てくる社長シリーズは素晴らしく、必ず「パッと行きましょう、パッと」と言いながらいい加減なことばかり言う三木のり平に乗せられて宴会芸の乗りでハレホレ踊るシーンなど何度みても大爆笑。シリーズを通じて森繁は歌や踊りを次から次に披露、もう森繁の一人舞台。かくし芸大会的な所もあって僕などウハウハワクワクであった。
淡路千景や加藤大介、若さムンムンと黒沢年男や桃屋のごはんですよのCMなんかをしていた鼻のデカい三木のり平、森繁社長に引きづり回される素人クサイ若い真面目社員小林桂樹も出てくる社長シリーズは素晴らしく、必ず「パッと行きましょう、パッと」と言いながらいい加減なことばかり言う三木のり平に乗せられて宴会芸の乗りでハレホレ踊るシーンなど何度みても大爆笑。シリーズを通じて森繁は歌や踊りを次から次に披露、もう森繁の一人舞台。かくし芸大会的な所もあって僕などウハウハワクワクであった。

