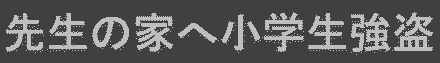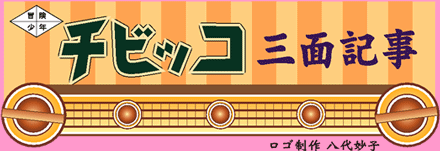|
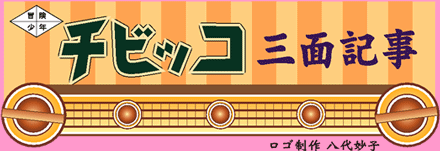
新聞に寄りますと!
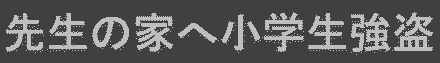
横浜市警K署は1日同市K区N町小学校6年生(15)を強盗容疑で検挙した。逃走中のM郡M町M(23)と共謀、卅日夜7時半横浜市K区長N町N小学校教員H(24)さん方留守宅に押入り、Hさんの母M(43)さんを短刀で脅し衣類数点を奪ったもの、同少年は6年生で犯行前同校にH先生が居残っているのを突止めてから同家を襲ったと自供している。(読売新聞、1952年2月1日/夕刊)
15歳の小学六年生というのも驚いた話だが、自分が教わっている教師の家に強盗に入るとは、昭和20年の終戦前まではまったく考えられないことである。この一件から、戦後にアメリカがもたらした自由主義教育が、日本人の価値観を一変させる力があったことがわかる。
戦前の児童は皇国臣民教育の下で教師への礼節、敬愛を強制され、目上の人間に口ごたえすることは許されていなかった。教師の命令は天皇陛下の命令と等しく、「天皇の赤子」である少国民(市民でも国民でもない存在だ)と教師とは擬似親子の関係である。歯向かうもの、抗弁するものには暴力(体罰)が待っていた。
アメリカの陸軍大臣だった、ジェファーソン・ディビスは「日本人ほど国家的観念の強いものは世界にその例を見ない。彼らは国家の為ならば喜んでその生業を犠牲とし、家族を捨て、命を投げ出すことをなんとも思っていない」と語ったことがあるが、まさに封建制度に狂信的な宗教要素を付け加えたものが戦前の日本を精神的に支配し、世界中を敵に回す戦争へ踏み切るほどの判断をさせた構成要素の一部となった(と、書いてはみたが日本が戦争に踏み切ったことを数行で論述解説することなどできっこないのです)。
教師の家に強盗に入ったこの事件は、戦前の教師と児童との擬似親子の関係性が敗戦によって切断され、「下克上」が起こることを意味している。
日本人の、個人や組織への忠誠心は、「封建社会」から培われた、「御恩と奉公」という形式から成り立っている。そのため、充分な報酬を与えないで、「奉公」だけを過剰に求めたとき、時間とともに関係は脆くなる。「何かのために心身を削り尽くすこと」は、あくまでも人間のまごころやそれに対する確固たる動機づけがあってこそ成り立ち、継続していくものである。天皇制という特殊な状況の下で約束されていた教師と児童の擬似親子関係という土台が、敗戦と共に希薄になっているにも関わらず、習慣や伝統性だけで、教師への忠誠心を継続させることはできなかったのだろう。
「奉公」は、まず社会的秩序の乱れを前提として、君主に尽くし、自己の暮らしの平穏や利益を保つために団結することからはじまったものであり、自己の利益なしに「御恩と奉公」という形態はありえない。室町中期から戦国時代にかけて「下剋上」という社会風潮が発展したのは、主君側がなすべきことをやらないで、家来へ「絶対服従」をもとめ続けたことが発端となった傾向が強いだろう。
天皇制の力が減少し、その影響下にあった、大人たちの力もまた減弱すると、児童を精神的に抑圧するものはなくなる。満足に主食も配給できない日本政府、瓦礫の山、街中ではアメリカからの進駐軍兵士が威張っている姿をみて、児童は社会が変わったことを感じ、これまでの伝統的権威を否定する心理になったであろう。
「下剋上」とは新しい形態への欲求であり、希望でもある。不満を抱えながらも現状に甘んじてきた人間が起す抵抗だ。それが、慣例や伝統に塗り固められた、不条理な体制への変革を求める場合に爆発する。しかし、その行為には常に、なんらかの犠牲が代償となるため、下克上決行までにはさまざまな精神的葛藤が生じる。その心理的移行について『忠誠と反逆』(丸山眞男/筑摩書房/1992)では以下のように述べている。
「組織・真理・信条など、いずれよ、それらが『型』へ停滞したとき、そうした型への順応を排する、生命の脱皮の過程として、まさに謀叛は肯定されている。けれどもその過程は同時に所与の自我へもたれかかろうという内的傾向性との不断のたたかいでもあり、『苦痛を忍んで』の解脱であって、けっしてたんに、外的束縛からの自我ののっぺりした解放感の享受ではなかった」
子どもが父親や教師をしのぎ倒す、これには不満の蓄積を解消し、未知への可能性をきりひらくという肯定的な側面のみならず、それまで築いてきた関係や生活との離別をも意味するのだ。その意味で、心に不満はあってもなかなか踏み切れるものではない。
●書きおろし
2003年5月6日更新
ご意見・ご感想は webmaster@maboroshi-ch.com
まで
第6回「運転をしたがる子どもたち」の巻
第5回「素人の催眠術はキケンなり」の巻
第4回「先生やりすぎです」の巻
第3回「懸賞の賞品で詐欺!」の巻
第2回「元祖! 飽食時代の本末転倒」の巻
第1回「『2B弾』のイタズラ」の巻
→
|