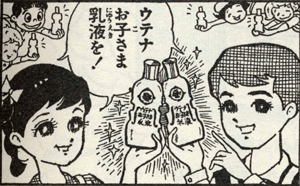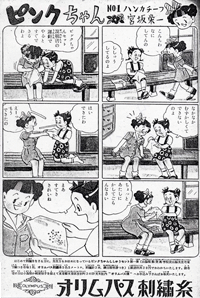第13回「通販広告の手法としてのマンガ」の巻 ●わかりやすいマンガ広告 少年少女向けの広告に、マンガを使用したものが増えたのは戦後である。 駆虫剤「アスキス」も『虫とチュン坊』というタイトルの四コマ広告マンガを昭和二九年に「少年」に掲載している。回虫などの寄生虫の虫下し剤だから虫=チュウで語感を考えて「チュン坊」としたのだろう。ついでにいえば薬剤名も駆虫を「明日期す」ということだろう。「アスキス」を発売していたナガ製薬は、もともと栄養剤「わかもと」を発売していた長尾欽彌が、昭和二十六年に設立した製薬会社。戦後、国民の多くがその日の食べものに困るなか栄養剤どころではなくなり売上が激減したので、当時結核とともに日本中に蔓延していた寄生虫に着目したのだ(しかし、駆虫薬で寄生虫がいなくなったために結局は倒産。実質的経営者であったのは長尾欽彌の妻。このヒトの人生がまたすごい。終戦後に近衛文麿が服毒自殺したときの青酸カリの入手ルートはここだと目されている)。手塚治虫調のほのぼのとしたマンガであるが、広告情報としてはマンガだけでは不安だったらしく、一ページの大半は活字による商品紹介である。 ●クスリから化粧品に 週刊「マーガレット」に昭和四十四年ころから掲載されていたのが「ウテナのウッちゃん」というマンガ広告。作者は野呂新平。登場人物は、ウッちゃん、テッちゃん、ナアぼう。ウテナの頭文字の駄洒落である。「ウテナお子さま乳液」など子ども化粧品の宣伝をしていた。子ども用化粧品のはしりは昭和二十八年に平尾賛平商店(レート化粧品ブランド)から出た「ジュニアクリーム」で、ビンの意匠は中原淳一がデザインしたという。そこから十二年経った昭和四〇年、ウテナが「ウテナお子さまクリーム」を発売して、高度成長時代に再度、子ども用化粧品の市場が開拓された。玩具会社も「お風呂セット」を出すなど昭和四〇年代終盤まで、大人への背伸び商品が少女向けに出されていったが、銭湯がなくなっていったこと、七〇年代以降にアトピーの子どもが増えたこと、性別世代をあまり問わない「花王ニベアクリーム」の登場などの理由が複合して、子ども化粧品市場は縮小していった。 「ロゼットセンガンパスタダヨー」と牧伸二のギター漫談にも歌われた、クリーム状洗顔料「ロゼット洗顔パスタ」(「ロゼット本舗 株式会社 詩留美屋」発売)も白子さんと黒子さんという、目玉がとても大きい女性主人公二人が、この商品の長所を、ゴルフ場やスキー場で語り合う形式のマンガであった。モデルは社内調達らしい(役員の奥さんとかね)。マンガ広告は昭和三十五年ころに製作開始、ニキビや肌の色が気になる中高生に人気があり、昭和四十年代には年間六〇〇万個も売り上げていた。 ●定番人気となったマンガ広告 江戸時代初期から四〇〇年にわたって伝えられてきた健康酒、「養命酒」のマンガ広告は昭和二十六年あたりから発見できる。養命酒のマンガ広告の特徴は、セリフがフキダシの中に入っているわけではなく、マンガは活字による説明の挿絵的な存在なのである。一種の紙芝居とでもいうべきか、学校を休みがちな病弱な子ども(当初は「正子さん」)が養命酒を飲んだら、元気はつらつ、顔色もよくなったという筋が多い。少年向けには「忍者も飲んでる養命酒」という、現在ではちょっと掲載できないようなパターンもあった(面白いけど)。近年では「こげパン」キャラも使用されていた。 マンガ広告で一番のロングランのキャラクターとしては「日ペンの美子ちゃん」ではなかろうか。少女漫画チックに瞳が大きい主人公が、一ページまるごとのマンガで活躍する「日ペンの美子ちゃん」。インパクトの強さと、学習雑誌への広告出稿もあってか、男の子にもファンは多い。美子ちゃんの誕生は昭和四十七年で、「月刊明星」の付録歌本に掲載する広告だった。日ペン講座を主宰する学文社によれば「美しい文字を書く女の子を中心に、書き文字の重要さや歴史と実績のある日ペンの講座の素晴らしさなどを、わかりやすくマンガで表現しようという企画」だったという。学文社の前身は、戦前の少年雑誌広告でおなじみだった「井上通信英語学校」(大正十三年創立)。学文社創立者である柴山格太郎は、英語学者の井上十吉の甥。通信教育で多くの青年に英語を学んでもらう機会を持ってもらおうとして、叔父の名前を冠した講座を設立した。そしてすでに昭和八年には日本ペン習字研究会の商号で井上千圃指導のペン習字通信教育を開始、これが「日ペン」である。 ●マンガ広告の行方 「マンガは人の頭の中に必ず残る」というのが、ロゼット洗顔パスタ発売元、詩留美屋の原敏三郎社長のことばだ。同社は売上、利益が上がっても従業員雇用や設備投資には使わず、広告にお金をかけたという。一時は、松下さえしのいだくらいだ。確かに、イメージ広告では商品の深いところまでは伝えられないし、テレビやラジオなどの電波メディアはその場限り。マンガという表現手法は商品の特徴をわかりやすく説明でき、しかもキャラクターを立てれば商品に対して親しみを持ってもらえる。一石で二鳥も、三鳥もあるのだ。 一部の業界商品においてマンガ広告が消えていったのは、昭和五〇年ころからだ。消費者保護の見地から、規格・表示等の適正化を進めていた厚生省がロゼット洗顔パスタの広告に「マンガは不謹慎だ」という通達をだしたのである。医薬品や、化粧品だからこそ効能効果をマンガでわかりやすく説明したい。しかしその表示手段に難色を示されてはどうしようもない。
●「小さな蕾」を改稿 2005年3月11日更新 第12回「子どものラジオ」の巻 |