| 
第17回「近所に出没したアヤシイひと」の巻
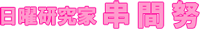
とんとんとんからりと、回覧板が廻ってきた時代、隣のおばさんは気軽に「奥さん、ちょっと煮干貸して」と鍋を片手にたずねてきた。子ども達が夜遅くまで遊んでいると「人さらいが来るぞ」と帰宅を促す近くの床屋のオヤジがいた時代、私たちが捨ててしまった濃密な人間関係は毛細血管のように伸びていた。そしてそのころはまだ、ヘンなおじさんと私たちは友達だった。
昭和四十年代の千葉、「イチロー」と呼ばれた中年男がいた。私が彼と初めて会ったのは千葉大付属病院の坂下の交差点だ。「ピピッーピッー」と白い笛を吹きながら、身振りよろしく彼は交通整理をやっていた。信号はきちんと作動し、自動車の通行はスムーズなのにかかわらずだ。なんだか旗も持ってたような。時々黄色信号で突っ切ろうとする車があると、物凄い勢いで笛を吹き、雷が落ちんばかりに説教をしていた。説教しているうちにまた青信号となり、後続の車からクラクションをならされているシーンはコメディ映画のようだった。
彼は上下、紺の作業服を着込み、白いヘルメットをかぶって念入りに長靴を履いていた。それなりの美学がある。警察官のまねであることは明らかで、もちろん違法なのは誰の目から見てもあきらかだが、中には颯爽とした彼の指示に従ってしまうドライバーもいるのが面白い。人間は一体、何を見て、何に従って生きているのか。ここには哲学的問題もある。
私は当時バスの車掌さんになりたかったので彼の気持ちは良くわかった。笛一つで自由に車を操るのはさぞかしやりがいのあることだったろう。ある意味で彼は街の人気者であった。共存していたんだなと今になって思うことが多々ある。 中学生になってから、ガード下をあるいていると、壁際に彼が寝ていた。一作業を終えた中年男が疲れて眠っているだけだった。
名前はわからない。だが、その恰幅が良く、色が浅黒い男は千葉駅前に立っていた。ボール箱の中箱を右手で前方に突き刺すように立っていた。服はよれよれながらも、毅然としてまっすぐ立っていた。その箱はお金を集金するための箱である。座らずに立ったまま、有象無象が足早に通り過ぎて行くさまを睥睨していた。
私はこの人を知っている。以前勤めていたスーパーに時たま現れ、うどんの玉五十三円を買っていくことがあったからだ。レジ係りの私が、真っ黒な手のひらに乗っかった五十三円分のお金をはがすように受け取る時、ニヤリとこの人は笑った。五十円玉の裏にはガムが付いていた。
あの人が数年後、駅前で超然と立っている。知っている誼ではあるが、私は無視して改札口へ向かって足を速めた。その頃はそんな雰囲気じゃなかったからだ。
漫画でデフォルメされたヘンなおじさんは「オジさんはね、オジさんはね……へっへへ」と壊れたレコード盤のようにつぶやいて八重歯を見せて笑うが瞬間、黒いコートの正面をバーッと開きあけた。ホントにそんなオジさんがいたのだろうか。だが、ほかの人の経験談をきいていると実在したような錯覚にも囚われる。そんなインパクトがあるほど、津々浦々に「怪しい人」は存在していたもようだ。
●週刊文春を改稿
2005年2月22日更新
ご意見・ご感想は webmaster@maboroshi-ch.com
まで
第16回「子ども会っていつからあるのか」の巻
第15回「子どもの移動距離と文化の深浅」の巻
第14回「あなたは塾にいきましたか」の巻
第13回「食べものを奪い合う子どもたち──カラーそうめんの希少価値はどこへ」の巻
第12回「いじるな、子どもは、レコードを」の巻
第11回「吹き矢でプー」の巻
第10回「くじ」の巻
第9回「カラーヒヨコがピヨピヨ」の巻
第8回「子どもの笑いのセンス」の巻
第7回「銭湯の下足札」の巻
第6回「日曜日のおでかけで作った綿菓子の甘い想い出」の巻
第5回「むかし日本の空き地には鬼がいた」の巻
第4回「マッカチンを知らないか……ザリガニ釣り」の巻
第3回「シスコーン、即席ラーメンの生喰い」の巻
第2回「落とし穴と犬のフン」の巻>
第1回「キミは秘密基地で遊んだか」の巻
→ |


