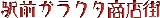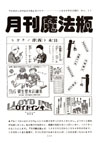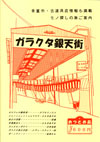上野にある不忍池を目の前に、娘を抱っこして自転車に乗っていました。たぶん今日、4月14日で東京の桜は終わりだな‥‥と思いながら、黄緑色の新芽がでてきた桜並木と、水面に浮かぶ桜の花びらを、ぼんやり眺めていると、なんだか現実感が薄れてきて、曜日も時間も、どこにいるのかも、わからなくなるような、不思議な感覚に陥ります。
平日のお昼だというのに、ボートに乗っている人や、ベンチで読書をする人、お弁当を食べる人、池のまわりに敷物を敷いて寝ている人、散歩にマラソンと、たくさんの人たちがいます。鳥たちものんびりと楽しそうですし、池の向こうにはスカイツリーも見え、今も昔も、不忍池は人を引き寄せる、都会の中のオアシスのような存在なのだなぁ‥‥なんて思いながら、約100年前の不忍池が写った絵葉書を思い出しました。


それは直径55ミリの小さな半円のガラスです。底はアルミで覆われ、「教育文具」、「特許出願」の文字があり、ガラスのほうからのぞくと、モノクロ写真が底に貼ってあります。写真には屋根と柱だけでつくられた六角堂のような建物と、それを眺めるように、椅子に腰かけた人たちが写っていました。そして、下には小さな文字で、「大正博覧會 第二會場 音樂堂」とあります。ナルホド。六角堂のような建物は音楽堂なのです。ちなみに文字は、すべて右横書きで書いてあります。博覧会で売られたグッズなのだと思いました。その後、絵葉書を見てビックリ仰天。前述に戻るわけです。そして、この音楽堂は、遠くにケーブルカーを眺めることができる、不忍池の畔に建てられていることを知りました。そんなことを思い浮かべながら、眺める不忍池は、歴史のようなものを感じられて、せつないような、なんともいえない気持ちになります。

実はこの文鎮には、もうひとつ魅力があります。ウランガラスなのです。真っ暗な場所でブラックライトを当てると、緑色に美しく輝くのです。本当は撮影をしてお見せしたいのですが、私は携帯用のブラックライトしか持っておらず、デジカメでの撮影が上手くできません。できるようになったら、ウランガラスについても、ご紹介したいと思います。
それにしても、「特許出願」とありますが、どの部分が特許なのか、番号が明記されていないのが残念です。たぶんアルミがはずれないように、写真をはめ込んでいるあたりだと思うのですが(単純な構造ゆえ、そこしかないでしょう。ただし、登録されたかはわかりませんが‥‥)、「教育文具」の文字も気になります。写真を入れ替えれば、いろんな種類の文鎮がつくれそうです。博覧会でも音楽堂だけでなく、エスカレーターや徳川式飛行機などの文鎮も売られたのかな? 当時はまだまだ写真も貴重な存在だったでしょうから、写す対象によっては、子供たちのあこがれになった、ステキな文鎮だと思います。